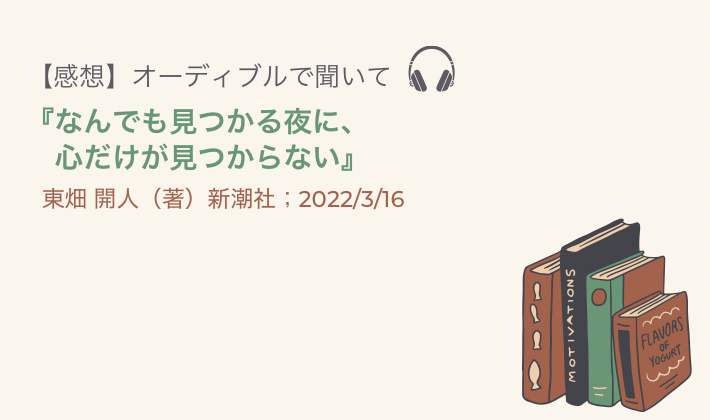みなさんこんにちは、読書を趣味にしたい公認心理師のだびでです。
今の社会は生きにくいと感じたことはありませんか?今回はそんな世の中を心理学の専門家がわかりやすい、そして奥深い表現で述べてる本を読みました。
作品情報
書名:なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない
著者:東畑開人
出版:新潮社(2022/3/16)
頁数:288ページ
著者について
東畑開人(ひがしはたかいと)さんは、1983年に東京で生まれた臨床心理士、公認心理師です。
京都大学教育学部を卒業し、同大学院教育学研究科の博士後期課程を修了しました。精神科クリニックでの勤務経験や十文字学園女子大学の准教授としての経験を経て、「白金高輪カウンセリングルーム」を主宰しています。
著書『居るのはつらいよ―ケアとセラピーについての覚書』(医学書院 2019)は、2019年に大佛次郎論壇賞を、翌年には紀伊國屋じんぶん大賞を受賞しました。そのほかにも『心はどこへ消えた?』(文藝春秋 2021、『雨の日の心理学ーこころのケアがはじまったら』(KADOKAWA2024)などを執筆しています。
本書の概要
家族、キャリア、自尊心、パートナー、幸福……。あらゆる悩みに耳をすませば聞こえてくるのは「ひとりぼっち」という苦しみだった。この自由で過酷な社会を、いかに生きるか。僕がいつもカウンセリングルームでやっていることをあなたとやってみたい。紀伊國屋じんぶん大賞受賞の臨床心理士が贈る、新感覚の“読むセラピー”。
『なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない』 東畑開人 | 新潮社
個人主義になりつつある現代の行きづらさを小舟に乗った夜の航海に例えて書かれています。
感想
本書では、心の処方箋と補助線の例え方が心に対する考え方として、非常にわかりやすい表現だと感じました。私たち心理士は心を論じる時、どうしても難しい言葉を使いがちになります。
小舟での旅をなぞりながら、本書はいくつかの場面で色々な角度から心に補助線を引いて、心を2つの側面に分けていきます。心という目に見えない抽象的なものを扱うために心理学は補助線を引いて枠を作って理解を試みています。そんな心理学の世界を
でも、本書は心理士でなくてもわかるような言葉を使って心の有り様について説明していました。私の仕事でも使えそうな表現もあって使わせてもらうことにしまた(^O^)。
とにかく出てくる物語(事例)に心動かされます。カウンセリングをするということはクライアントにとってもカウンセラーにとっても嬉しいこと苦しいこと、紆余曲折があって、進んでいくということを考えさせられます。
カウンセリングで右肩上がりに生活が改善されない様子、カウンセラーが上手くいっていると思っていても、実は肝心の何かが取り扱われていない、このような部分がカウンセリングの難しい部分でもあり、醍醐味なんだなと感じました。
そして、私がこんな風にクライエントの物語に寄り添いたいから心理士になったんだと再認識することができました。