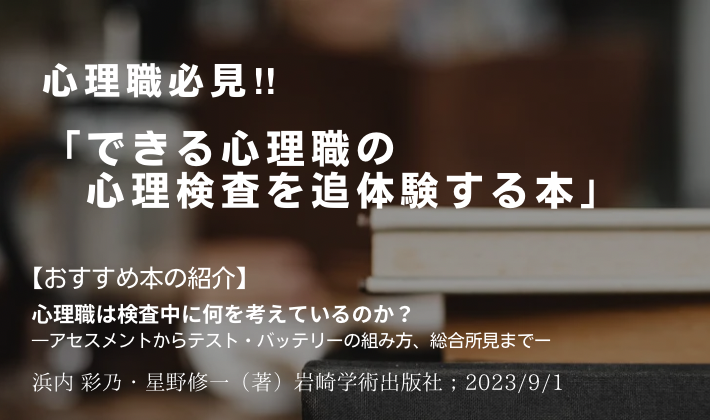こんにちは、公認心理師のだびでです。
みなさんは心理検査についてしっかりと勉強したものの、実際に仕事として取り組む際に自信を持てないという悩みをもったことはありませんか?私は大学院を修了して就職した際は、この悩みを持っていました。
また、ある程度心理検査の実施に慣れたけど、所見を書く段階で筆が進まず、考え込んでいるうちに時間だけが過ぎていく、そんな経験をしている方も多いのではないでしょうか。
今回は「心理検査のコツを知りたい」「心理検査ってどうやってやるの?」と感じている人におすすめの本を紹介します。
こんな方におすすめ
- 心理職を目指す大学生・大学院生
- 新米心理師(公認心理師、臨床心理士を取り立ての人)
- 心理検査を業務としている心理職
など、心理検査について勉強したい方におすすめです!
本書の概要
作品情報
書名:心理職は検査中に何を考えているのか?―アセスメントからテスト・バッテリーの組み方、総合所見作成まで
著者:浜内 彩乃 ・ 星野 修一
出版:岩崎学術出版社(2023/9/12)
頁数:192ページ
本書は猫川先生の1つの事例に基づき「情報収集」から所見作成、本人へのフィードバックまでの手順と思考プロセスが書かれています。
「はじまりから終わりまで、一連の流れをたどって読み解かなければ、ほんとうの「検査力」は身につかない――」
クライエントとの出会うとき、テスト・バッテリーを組むとき、心理検査を実施するとき、所見を書くとき……。
心理検査にまつわるさまざまな場面で、心理職は何を考え、何に悩み、どのようにアセスメントを構築しているのか――?
本書は心理検査に習熟した心理職の思考プロセスを疑似的に追体験できるように構成。各心理検査のマニュアルと解釈の専門書とを有機的につなぎ、検査データとリアルなクライエントの様子とをいきいきとつなぐことを目指した実践的な1冊。
心理職は検査中に何を考えているのか?―アセスメントからテスト・バッテリーの組み方、総合所見作成まで | 浜内 彩乃, 星野 修一 |本 | 通販 | Amazon
※本書はWAIS-Ⅳ、P-Fスタディ、バウムテスト、ロールシャッハのテストバッテリーを組んだ事例が紹介されています。ロールシャッハテストはエクスナー法(包括システム)、バウムテストは1枚法で紹介されています。私はロールシャッハテストを片口法バウムテストを2枚法・3枚法で実施していますが、本書は各々の検査の事細かい解釈ではなく、心理検査全体のプロセスに焦点を当てているので非常に参考になりました。
私が読んで学べたこと
本書を読む前の私は、十分な情報収集を行っていませんでした。しかし、この本を通じて心理検査は準備段階から始まることを学び、情報収集に対する姿勢がより丁寧になりました。また、心理検査全体を意識することで、検査を実施する際にはその目的に応じた行動観察を心掛けるようになったような感じがします。
本書を読むことで検査の目的に基づいて解釈や思考を整理し、所見を作成することで以前よりも効率的に心理検査の過程を進めることができるようになりました。
おすすめポイント
今回は私が読んで皆さんにおすすめしたい理由を3つ紹介します!
心理検査の基礎が勉強できる
本書は第一章で心理検査の種類や何のために実施されるのかなどの説明が丁寧にされています。そのため、心理検査の知識があまりない初学者の方でもわかりやすく学ぶことができます。
また、心理職が働いている各機関で他職種(医師・看護師・教師など)に心理検査の基礎をわかりやすく説明するためにも非常に参考になります。
所見に応用しやすい言葉で解釈が載っている
心理検査の実施本や解釈本は、専門用語を並べて書いていることが多いです。しかし、心理検査の報告書は読み手がわかる言葉で書く必要があるので実施本や解釈本に書かれている専門用語をそのまま使うわけにはいきません。また、出版年が古くて現代を生きる心理職には読みとりずらい本であったり、日本語訳された本だから理解しづらかったりするものもあります。
本書は各検査の専門用語を少し砕いた表現で説明しているため、用語理解に非常に役に立ちます。そして、日常的に使用する現代的な表現で構成されているため、所見作成時の語彙としても参考になるので所見作成時に使えるところもポイントです。
情報収集から総合所見までのプロセスがすべて載っている!
またもや解釈本との比較になってしまいますが、解釈本の中には情報収集の方法やスケジュール設定について詳述しているものは少ないように思います。事例が紹介されていることもありますが、実際の心理検査の参考にするには難しい場合もあります。
本書では、他の本では省略されがちな「どのように進めれば良いか」といったポイントを追体験することができます。また、検査の実施からフィードバックに至るまでのプロセスが詳しく記載されており、心理職がどのような思考を持って心理検査を行うのかを細かく理解することができます。なので、順を追って読むだけで、心理検査のプロセスをイメージできるようになって見通しを持って心理検査を行えるようになります。
最後に
いかがだったでしょうか。本書は心理検査を行う心理職の皆さんにおすすめの本を紹介しました。各検査の実施本・解釈本に加えて持っておきたいと思えるような1冊です。ぜひ、皆さんも実際に本書を読んで「できる心理職」が心理検査中に何を感じているのかを体験してみください。