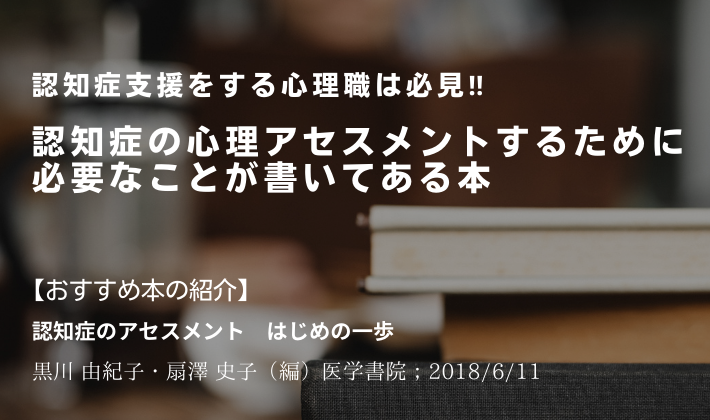みなさんこんにちは、公認心理師のだびでです。
認知症患者を支援する機関において、心理職のニーズは大きくなっています。しかし、臨床心理学専攻の大学院では、認知症についてはあまり詳しく勉強しません(多分)。
公認心理師試験で必死に脳の機能や認知症の種類について勉強した日々が懐かしいです。
今回は認知症の方と関わるけど、あまり認知症や脳の機能に詳しくないという方におすすめの本を紹介します。
作品情報
書名:認知症のアセスメント はじめの一歩
著者:黒川 由紀子・扇澤 史子
出版:医学書院(2018/6/11)
頁数:184ページ
こんな方におすすめ
今後心理職のより深いかかわりが求められる「認知症」。そのアセスメントから支援への導き方までを学べる本が登場。検査結果の背景に脳のどんな障害があるのか、イラストと豊富なデータ、事例でしっかり解説し、公認心理師対策にも生かせる「神経心理学」の基本が身につく。病院や地域、福祉施設など様々な場面でのアセスメントと支援、報告書の書き方も明快に提示。認知症にかかわる心理職が“はじめの一歩”を踏み出せる1冊!
認知症の心理アセスメント はじめの一歩 | 書籍詳細 | 書籍 | 医学書院
認知症の方を支援する心理士が必要となる知識の多くが載っています。まさしく、認知症患者の支援のはじめの一歩としてふさ欲しい本です。そして、ずっと使い続けることのできる内容になっています!
おすすめポイント
次に本書のおすすめポイントを紹介します。
カラーイラストでわかりやすい
本書はオールカラーで書かれていて視覚的に非常にわかりやすい本です。文章も太字で強調されていたり、段落が細かく区切られていたりと読みやすいです。
全体的なデザインが見やすく、良い意味で小学生の頃の教科書のようです。読むことに対して抵抗感が少ないです。
なのに、内容は専門的でしっかりしています。
脳機能と認知症についての基礎知識がわかる
認知症患者の支援を行う上で心理士に必要になる知識は、脳のどの部位がどのような機能を果たしているのか。そして、認知症の種類とどのような違いがあるかです。
本書はこの2点をしっかりと抑えています。初学者にもわかりやすいような言語表現とイラストによる解説、具体的な例が述べられています。
本書があれば心理士に必要な基本的な認知症の知識を身につけることができます。
認知機能検査で何を測定しているのかわかる
臨床現場では心理職が認知症患者に関わるタイミングとして、認知機能検査を行うということが非常に多いです。誰でも検査を行うことは可能ですが、検査に抵抗感が強い人もおり、治療構造的に心理職が実施する機関が多いのではないでしょうか。
本書は心理士が認知症患者のアセスメントをするための知識に焦点が向いています。特に、MMSEやHDS-Rの正誤がどのような機能と関係しているか書いてあることが非常に参考になります。
また、認知症ごとに認知機能検査でどのような特徴が現れるかが書いてあるため、点数だけてはなくどの機能が低下しているのか、どの認知症の可能性があるかなどを考えることができるようになります。
感想
この本は認知機能検査の所見を書く時は、いつもこの本を開きながらいつも書いています。私が認知機能検査をする上で必須の本となっています。
公認心理師の勉強範囲で苦手だった脳の機能や認知症の症状についても本書を読みながら所見を作成している中に得意分野の1つになっていきました。
読み進めても辞書として読んでも重宝している本です。