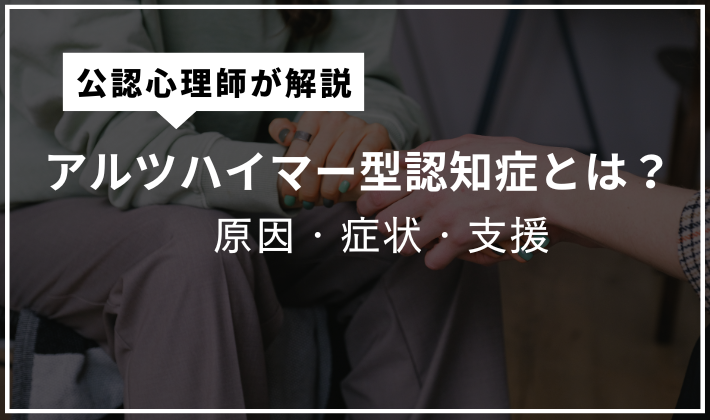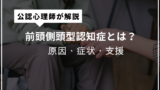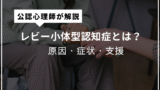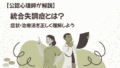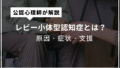みなさん、こんにちは!公認心理師のだびでです。日本では今、高齢者が増えていて、それに伴って認知症の方も増えています。そのため、認知症の方をサポートするために、私たち心理職の専門知識やスキルがより一層必要とされています。
「もしかして認知症かも?」と心配している方やご家族は多いと思います。でも、認知症にはいろいろな種類があり、それぞれ特徴や症状が違います。ただ単に「認知症」とひとくくりにはできないんです。認知症の種類によって、症状の出方や進み方、必要なサポートの方法も大きく変わってきます。
今回は、認知症の中で最もよく見られる「アルツハイマー型認知症」について説明します。日本では認知症の方の約6割がこのタイプです。この病気の特徴や症状を知ることは、ご本人やご家族にとってとても大切なことです。このブログを通して、アルツハイマー型認知症についての理解を深めていただければ嬉しいです。
アルツハイマー型認知症の原因
アルツハイマー型認知症(AD)は、「βアミロイド」や「タウタンパク質」という物質が脳内に溜まってしまうことで起こる病気です。本来ならこれらの物質は体が処理するはずなのですが、溜まってしまうと周りの神経細胞を傷つけ、少しずつ脳の働きが悪くなっていきます。特に記憶をつかさどる「海馬」や考えることを担当する「大脳皮質」の神経細胞がダメージを受けると、物を覚えたり、考えたり、判断したりする力に問題が出てきます。
この病気は年を取るほど発症しやすくなり、特に65歳以上の方に多く見られます。若い人が発症する「若年性認知症」の場合もありますが、それはあまり多くありません。日本では認知症の人の約6~7割がこのアルツハイマー型だと言われています。高齢者が増えている日本では、今後もアルツハイマー型認知症の患者さんは増えていくと考えられています。
アルツハイマー型認知症の症状
アルツハイマー型認知症は、少しずつ症状が進行する脳の病気で、治療が難しいものです。高齢者の物忘れや認知機能低下の主な原因となっています。この病気は記憶力や思考力、日常行動に影響を与え、進行すると食事や着替えなどの基本的な生活動作にも支障をきたします。
アルツハイマー型認知症の症状は大きく次の2つに分類されます。
- 脳の機能が低下する中核症状
- 中核症状によって現れる周辺症状(BPSD)
中核症状(認知機能障害)
アルツハイマー型認知症の中核症状は、主に次の4つに分類されます。
- 記憶障害
- 見当識障害
- 実行機能障害
- 視空間障害
記憶障害
まず初期段階で気づかれやすいのは、最近のことを覚えておく力の低下です。特に新しい情報を記憶する能力(記銘力)が弱くなります。患者さんは最近起きたことを思い出せなくなり、「同じ話を何度もする」「財布や鍵をどこに置いたか忘れる」「約束や予定を忘れる」といった症状が見られます。大切なことでも、たった数分前の出来事を覚えていられないこともあります。
「おじいちゃん、さっき食事したよね」「それ、さっきも聞いたよ」など、記憶障害のある方によく言われる言葉です。本人はこうした症状に気づいていないことが多く、他の人に指摘されて初めて自覚することもあります。不思議なことに、昔の記憶は比較的よく残っていることが特徴です。
見当識障害
時間・場所・人間関係がわからなくなる症状です。これは多くの人が「認知症っぽい」と感じる典型的な症状です。
時間の見当識障害(時間の感覚がわからなくなる):今日が何月何日か、何曜日かといった基本的な時間の感覚が少しずつ失われていきます。カレンダーを見ても日付がわからなくなったり、昼と夜の区別がつかなくなったりすることも。そのため、「昨日どこに行ったか」や「明日何をするか」といった時間に関する情報を覚えておくことが特に難しくなります。
場所の見当識障害(場所がわからなくなる):場所の認識が難しくなり、一人で外出すると家に帰れなくなって道に迷うことがあります。特に慣れない場所では方向感覚を失いやすく、以前は問題なく行けていた場所でも迷子になることがあります。こうした状況は本人にとって強い不安や恐怖を感じさせ、さらに混乱してしまうことがあります。
人の見当識障害(人がわからなくなる):近所の人の顔を見ても誰かわからなくなったり、長年一緒に暮らしてきた家族の顔や名前さえも認識できなくなったりします。
特に子どもや孫の名前や顔を忘れてしまうことは、家族にとって非常に悲しい出来事ですが、これも見当識障害の特徴的な症状の一つです。
実行機能障害
計画を立てたり順序立てて考えたりする力が弱くなり、判断も難しくなります。これは「今までできていたことができなくなる」症状です。
例えば、いつも作っていた料理の手順がわからなくなったり、銀行での手続きの仕方がわからなくなったりします。また、いくつのことを同時にするのが難しくなり、一つのことに集中するのも大変になります。日常生活で問題が起きたときに対処する力も弱まり、予想外の状況に対応できなくなります。この「実行機能障害」は認知症の初期から現れることがありますが、物忘れや時間・場所がわからなくなる症状ほど目立たないため、家族や周りの人が気づくのが遅れがちです。
視空間障害
視空間障害とは、周りの物の位置や形、距離などを正しく把握することが難しくなる症状です。
例えば、文字がうまく書けなかったり、服の前後がわからなくなったり、家具にぶつかりやすくなったりします。また、車の運転で距離感がつかめなくなる、着替えの時に服の向きがわからない、食事の時に食器の使い方がわからなくなるなどの困難も生じます。この症状は見落とされがちですが、日常生活を自分で送る上で大きな影響がある重要な症状です。
周辺症状(BPSD)
行動・心理症状(BPSD)は、認知症によって現れる様々な行動や心理面の変化のことです。これは英語で「Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia」と言い、頭文字をとってBPSDと呼ばれています。認知症の脳の変化によって、様々な行動や気持ちの変化が起こるのです。このBPSDは人によって大きく異なります。同じアルツハイマー型認知症でも、ある人はイライラしやすくなり、別の人は不安が強くなるなど、その現れ方は一人ひとり違います。
ここからは、アルツハイマー型認知症の方によく見られるBPSDについて、具体的に紹介していきます。
徘徊
時間や場所がわからなくなる症状によって、自分がどこにいるのかわからなくなったり、どこかに行こうとしても途中で何をしようとしていたか忘れてしまったりすることがあります。そのため、外から見ると目的もなくただ歩き回っているように見える「徘徊」という行動が現れることがあります。 ですが、実は本人の中では「家に帰りたい」「仕事に行きたい」など、はっきりとした理由があって歩いていることが多いのです。
物取られ妄想
物取られ妄想とは、自分がしまったものを忘れてしまい、「誰かが盗んだ」と思い込んでしまう症状です。アルツハイマー型認知症の方は記憶障害により、物をどこに置いたかを覚えていないことがよくあります。しかし、自分が忘れたという自覚がないため、「誰かが盗った」という妄想に発展してしまいます。
また、本人が「次は盗まれないように」とタンスの奥やソファの裏など見つかりにくい場所に物を隠したことを忘れてしまい、家族と一緒に探しても見つからないこともよくあります。
感情コントロールの障害(感情失禁)
感情コントロールの障害とは、感情をうまく調整できなくなることです。ちょっとしたことで急に泣いたり、怒ったりすることがあります。これは脳の前頭葉の働きが弱くなり、感情をコントロールする力が低下するためです。アルツハイマー型認知症が進むと、自分の気持ちの表し方をコントロールすることが徐々に難しくなります。例えば、テレビの少し感動的な場面でも大泣きしたり、ちょっとした声かけに対して思いがけず強く怒ったりすることがあります。このような感情の変化は急に現れることが多く、家族や介護者にとって対応が難しい症状です。また、感情の上下が激しくなるだけでなく、反対に何事にも関心を示さなくなったり、やる気がなくなったりすることもあります。
アルツハイマー型認知症の治療
アルツハイマー型認知症は現時点では完全に治す方法がありません。治療の目標は症状の進行をゆっくりにしながら、その人がその人らしく生活できるよう支援することです。
薬物療法
現在のアルツハイマー型認知症の治療薬には限りがあり、使える患者さんも少ないのが現状です。いくつかの薬は開発されていますが、完全に治す薬はまだありません。そのため、多くの場合は眠れない、落ち込むなどの行動・心理症状(BPSD)を和らげるための薬が処方されることがあります。
環境調整
薬による治療と同時に、心理的・社会的なサポートもとても重要です。認知機能を鍛える訓練や、音楽を使った療法、昔の思い出を語り合う回想法などが、生活の質を高めるのに効果的です。
本人が安心できる環境作りも大切です。日常の中での混乱や不安を減らし、安全で予測できる環境を整えましょう。具体的には:
- 家具の配置はなるべく変えない
- よく使うものは見つけやすい場所に置く
- 毎日の生活リズムを一定に保つ(起床時間、食事時間など)
- カレンダーや時計を見えるところに置いて、今の季節や時間がわかるようにする
- 夜は程よい明るさにして安心して眠れるようにする
こうした小さな工夫が、認知症の方の生活の質を大きく向上させることがあります。
家族支援
アルツハイマー型認知症の方を支える家族のサポートもとても重要です。家族は毎日の介護で心身ともに疲れがたまりやすく、適切なサポートがないと家族の健康も認知症の方の健康も損なわれてしまうことがあります。
地域には「家族会」という認知症の方の家族が集まり、お互いの経験や悩みを共有できる場所があります。また、認知症の進行過程や症状、対応方法などを学べる機会も提供されています。こうしたサポートは介護する家族の負担を軽減し、認知症の本人と家族の両方が良い生活を送れるよう助けてくれます。長期的な視点で、家族全体の幸せを支える総合的なサポートが大切なのです。
公認心理師の関わり
現在、私たち公認心理師は認知症の方に直接関わる機会があまり多くありません。これは今後の支援の形として検討するべき課題です。
今のところ、公認心理師の主な役割は、認知症の検査と家族などへのサポートが中心となっています。
神経心理学検査
公認心理師は認知症であるかの診断や認知症の程度を見るために認知機能検査を実施します。認知機能検査は本人の状態に合わせた支援をするためにも重要な役割を果たしています。
よく実施される認知機能検査をいくつか紹介します。
- 改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDSーR)
- MMSE
- 前頭葉評価バッテリー(FAB)
- アルツハイマー病評価尺度(ADAS)
- Clinical Dementia Rating(CDR)
- 時計描画テスト(CDT)
この検査はよく誤解されますが、私たちが行う検査は自動車教習所で実施される認知機能検査とは全く異なるものですので注意が必要です。
また、検査内容は調べれば確認できますが、事前に内容を知っていると正確な評価ができず本人のためになりません。認知症の相談に行く際は、検査内容を事前に調べたり、他の人に教えたりすることはお勧めしません。
本人・家族支援
心理検査の結果をわかりやすく分析し、その方の認知機能に合わせた日常生活の工夫を具体的に提案します。また、医師や看護師、作業療法士、ケアマネジャーなどの専門家と協力して、総合的な支援計画を作ります。さらに、検査結果から認知症の方が「まだできること」や「得意なこと」を見つけ出し、それを活かせる環境づくりも提案します。
認知症の家族を介護する方の心の負担はとても大きく、「介護うつ」や「燃え尽き症候群」になってしまうことも少なくありません。そのため、家族へのサポートとして、ストレスの対処法や効果的な接し方をアドバイスしたり、気持ちを整理するためのカウンセリングを行ったりします。また、同じ悩みを持つ方々が集まる「家族会」を紹介したり、今後の見通しについての情報を提供したりすることも公認心理師の大切な役割です。
まとめ
アルツハイマー型認知症は特別な病気ではありません。高齢化が進む日本では、多くの方が経験する可能性がある一般的な状態です。認知症全体の6~7割を占めるこのタイプについて理解することで、ご家族や周りの方への接し方が大きく変わります。
最も大切なのは、「認知症になると何もわからなくなる」という間違った考えをなくすことです。記憶に問題があっても、感情や大切な思い出は残っています。その人らしさも変わりません。症状の特徴と本人の人生を知ることで「なぜそういう行動をするのか」が理解でき、適切な支援ができるようになります。
認知症の方は「困った人」ではなく「困っている人」なのです。私たち周りの人間が理解を深め、暮らしやすい環境を整えることで、認知症の方も安心して生活できる社会を一緒に作っていきましょう。認知症の方の尊厳を守り、その人らしい生活を支えることが、これからの社会には必要です。
参考文献
黒川由紀子・扇澤史子(編)(2018)『認知症の心理アセスメント はじめの一歩』医学書院
河野和彦. (2016). ぜんぶわかる認知症の事典: 4大認知症をわかりやすくビジュアル解説. 成美堂出版
川畑智 (2021). マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界. 文響社.