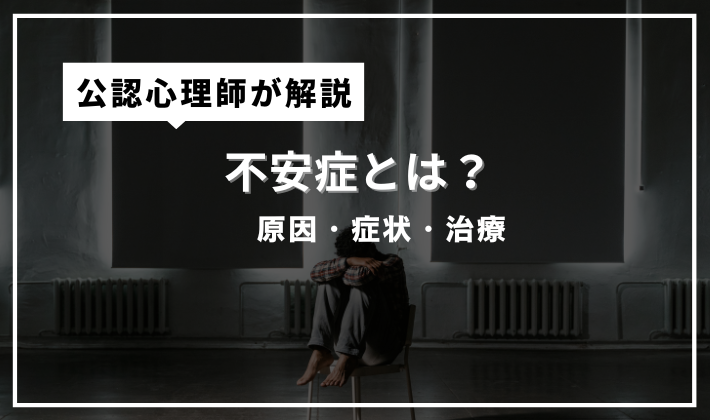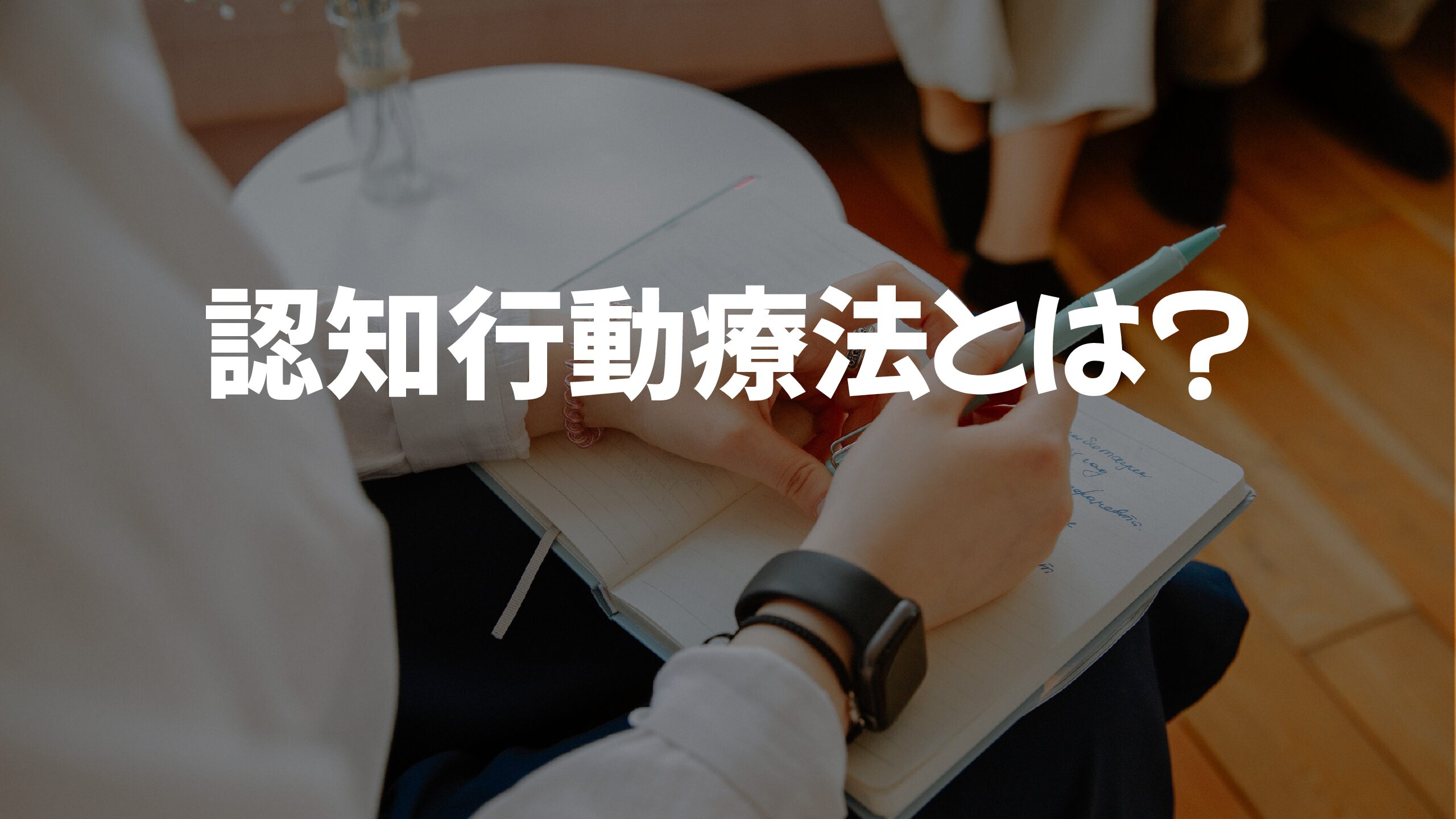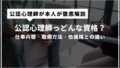不安は誰もが日常で感じる自然な感情です。試験前の緊張や大切なプレゼン前のドキドキなど適度な不安は私たちのパフォーマンスを高める役割も果たします。
しかし、その不安があまりにも強く、長く続き、日常生活に支障をきたすようになると、それは「不安症(不安障害)」という心の健康問題として考える必要があります。
日本では約15人に1人が一生のうちに何らかの不安症を経験すると言われており、非常に身近な心の問題です。
今回のブログでは、公認心理師の立場から「不安症」についてできるだけわかりやすく解説していきます。特に「パニック症」「社交不安症」「広場恐怖症」を中心に、症状の理解から治療・支援のポイントまでまとめました。
早期発見と適切な支援によって症状の改善が期待できますので、正しい知識を持つことがとても重要です。
不安症とは?
脳の働きのバランスが一時的に崩れ、不安反応が過剰に起こってしまう状態です。不安は本来、危険から身を守るための自然な反応ですが、強く出すぎると日常生活に支障をきたします。
大切なのは、早めに気づき、適切な支援につなげることです。
よくある勘違いですが、不安症は「気が弱い」「性格の問題」といったものでは決してありません。
不安症の原因
不安症は「これだけが原因」という単純なものではなく、いくつかの要因が重なって起こると考えられています。
- 生物学的な要因: 脳の中の「扁桃体」という不安を感じる部分が過敏になっていたり、セロトニンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質のバランスが崩れていることがあります。
- 心理的・社会的な要因: 強いストレスやトラウマ体験、あるいは「不安を感じる出来事=危険」と学習してしまった経験が関係することもあります。
- 考え方の傾向(認知的要因): 「最悪のことを想像してしまう」「曖昧なことに耐えにくい」などの思考パターンも不安を強める一因になります。
- 生活習慣・環境要因: 睡眠不足や生活リズムの乱れ、慢性的な疲労なども影響します。
こうした要因が重なり合い、「不安が過剰になりやすい脳の状態」が続いてしまうのです。
不安症の主な症状
人によって感じ方はさまざまですが、大きく分けて「心の症状」と「体の症状」があります。
心の症状
- 将来のことを過剰に心配してしまう
- 特定の場面や人を怖く感じる
- 「不安になることが不安」という予期不安
- 不安な場面を避けるようになる(回避行動)
- 危険な情報ばかりに目が行く(注意の偏り)
体の症状
- 動悸、息苦しさ、胸の圧迫感
- めまい、ふらつき
- 発汗や震え
- 肩や首のこり、頭痛
- 胃腸の不調(腹痛、吐き気、下痢など)
- 寝つきが悪い、眠りが浅い
不安症の主なタイプ
不安症にはさまざまな種類があります。今回は主な不安症である3つを紹介します。
1.パニック症
パニック症は、突然、理由がわからずに強い恐怖感に襲われ、同時に動悸や息苦しさ、めまいなどの体の症状が出る「パニック発作」を繰り返す状態のことです。
発作は通常10分から30分ほどで落ち着きますが、「またあの怖い発作が起きたらどうしよう」という不安が強くなり、発作が起きそうな場所を避けたり、外出を控えたりするようになることがあります。
2.社交不安症(社交不安障害)
社交不安症は、人前で話をしたり、初めての人と会ったり、周りから注目される場面で、とても強い不安や緊張を感じてしまう状態です。ただの緊張とは違い、その不安の強さで日常生活に困ることが特徴です。
この症状の根っこにあるのは、「失敗したらどうしよう」「恥ずかしいと思われるかも」「変だと思われたらどうしよう」といった、他人からどう見られるかへの強い恐れです。こうした不安で頭がいっぱいになり、人と関わることや社会的な場面を避けるようになることもあります。
3.広場恐怖症
広場恐怖症は、ある場所や状況で「何かあってもすぐに逃げられない」「助けを呼べない」などの不安を強く感じてしまい、そうした場所を避けるようになる状態です。
たとえば、人混みや混雑したお店、電車・バス・飛行機などの公共交通機関、エレベーターやトンネルなどの閉じた空間、あるいは一人での外出などに対して、強い不安や恐怖を感じるようになります。
治療と支援
不安症の治療では、非薬物療法と薬物療法を組み合わせることが多く、症状の程度や本人の希望に応じて柔軟に調整していきます。
また、周囲の理解やサポートも回復には欠かせません。焦らず、自分のペースで取り組むことが大切です。
非薬物療法
カウンセリングは不安症の治療において中心的な役割を果たします。専門家との対話を通じて、不安の理解を深め、対処法を学んでいきます。
カウンセリングには様々なアプローチがありますが、その中でも認知行動療法(CBT)は特に効果が実証されている方法の一つです。
- 不安を引き起こす「考え方のクセ」を見直し、より現実的でバランスの取れた視点を育てていきます。
- 段階的曝露により、避けていた場面に少しずつ慣れていく練習を行います。
- リラクセーション法や呼吸法など、不安をコントロールする具体的なスキルを身につけます。
薬物療法
薬物療法では、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などを用いて脳内の神経伝達物質のバランスを整え、必要に応じて抗不安薬を短期的に使用しますが依存性に注意しながら慎重に用います。また、カウンセリングなどの非薬物療法の効果を高める補助的な役割も果たします。
日常生活でできる工夫
- 規則正しい生活リズムを整え、十分な睡眠を確保する
- 適度な運動習慣を取り入れる(散歩などの軽い運動でも効果的)
- カフェインやアルコールの摂取を控えめにする
- 信頼できる人に気持ちを話す機会を持つ
カウンセリングや病院に行くことに抵抗がある、1人で何がやりたいという方はセルフケア本がおすすめです。
まとめ
不安症は「弱さ」ではなく、心身のシステムが少し過敏になった状態です。
適切な治療と支援により、多くの方が再び安心して生活を取り戻しています。もし不安が強くてつらいときは、ひとりで抱え込まず、医療機関や相談機関にご相談ください。
少しずつ、一緒に回復への道を歩んでいけます。