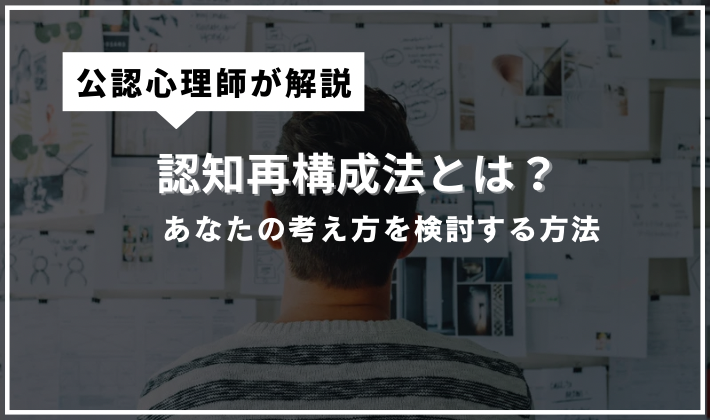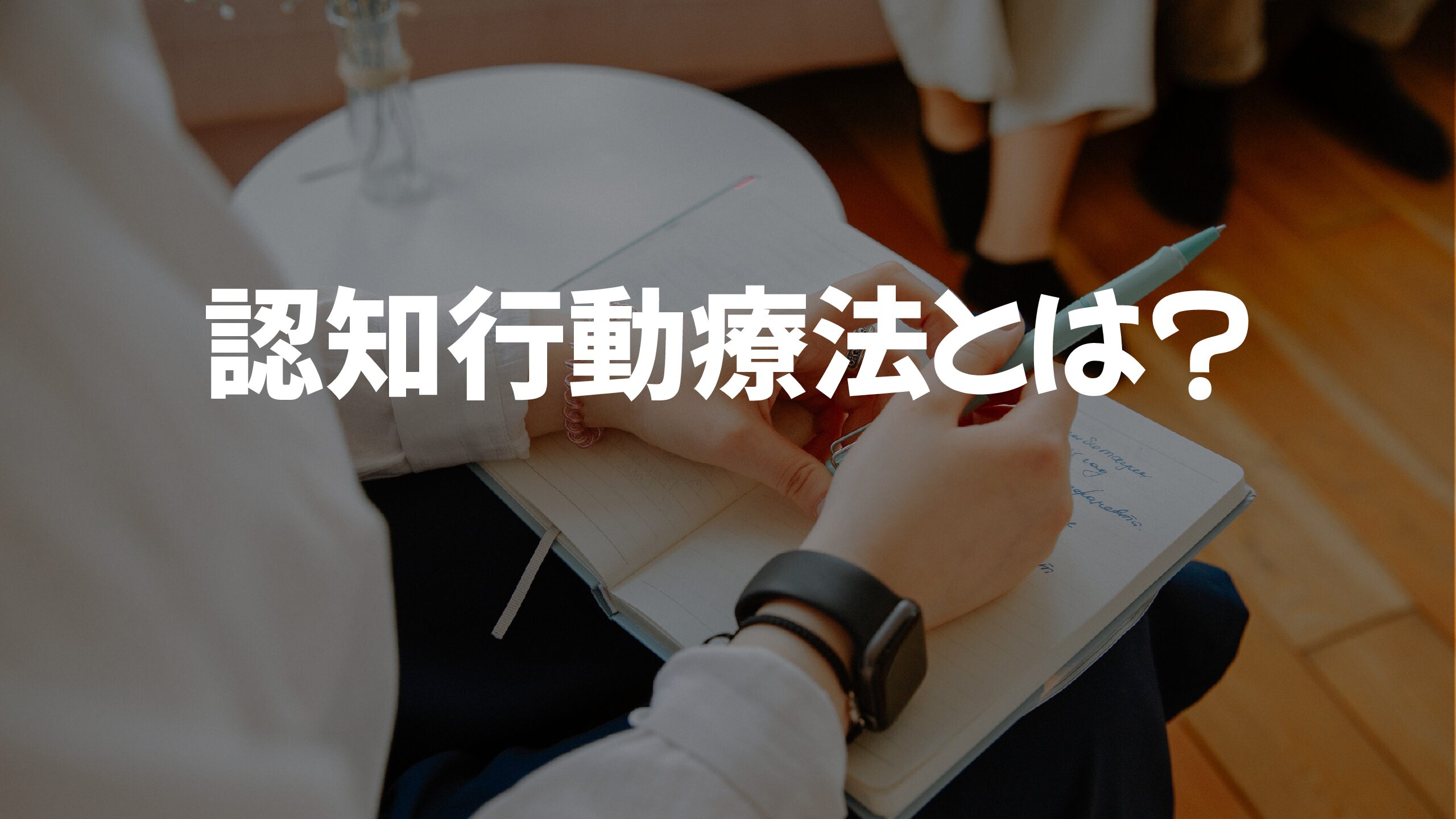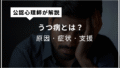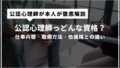こんにちは!公認心理師のだびでです!
ある出来事が起きたとき、思わず「もうダメだ」「どうせうまくいかない」といった考えが頭に浮かび、気分が落ち込んだり不安になったりした経験はありませんか?
実は私たちの「考え方(認知)」は、気分や行動に大きな影響を与えています。特に気分が落ち込んでいるときや不安が強いときには、考え方が必要以上にネガティブになりがちです。
この記事では、認知行動療法(CBT)の中心的な技法のひとつ、「認知再構成法」をご紹介します。
認知再構成法の考え方:なぜ思考を見直すのか?
認知再構成法は、出来事に対する「役に立たない思考」——気分を落ち込ませる思考や不安を強くする思考——を振り返って検討する方法です。
認知再構成法を行うことで
- 気分の改善
- 自己理解
- 次に起こすべきアクションの設定
に役立ちます。
認知再構成で検討する思考「自動思考」
私たちは日々の出来事に対して、瞬間的に「自動思考(automatic thoughts)」と呼ばれる考えが浮かびます。これは、意識しなくても自然と頭に浮かぶ考えで、気分や行動と大きく関係しています。
たとえば、仕事でミスをしたときに「自分はダメな人間だ」という自動思考が浮かぶと、落ち込みや自己否定につながります。このような自動思考が現実とズレていたり極端だったりすると、私たちの感情や行動も偏ったものになってしまいます。
認知再構成法では、この自動思考を見直し、現実的でバランスの取れた「適応的思考」に置き換えることで、ネガティブな気分や非建設的な行動の悪循環を断ち切ることを目指します。
認知再構成法のやり方:7つのステップ
認知再構成法は、感情的な思い込みに流されず、科学者のように冷静に自分の思考を検証していく方法です。今回は、有名な「7つのコラム」のステップを紹介します。
1. 自動思考を捉える場面を設定する
気分の落ち込みが続いているきっかけとなったことや、1週間の中で一番辛かったことなど、「気分が大きく動いたイベント」を思い浮かべます。そして、その一連のイベントの中で最も感情が強かった瞬間を、写真を撮ったように思い浮かべて書きます。
例)
「〇月〇日15時に上司から呼び出されて、資料のミスを指摘された。その後、私は自分の席に座って泣いてしまった」
2. その時の感情を書き出す
具体的な場面を設定したら、その時に感じていた感情を書きます。感情とは一言で表現できる心の動きのことです。
- モヤモヤ
- 怒り
- 不安
- 悲しい
などです。
複数の感情があったら、絞らずにすべて書いてください。そして、その感情が今までの経験の中で何%の強さであるかも書いていきます。
例)
・モヤモヤ(50%)
・悔しい(70%)
・悲しみ(80%)
・怒り(30%)
3. 自動思考を書き出す
状況と感情を書いたら、次は自動思考です。自動思考はその瞬間にパッと頭の中に浮かんだ考えのことです。
状況を読み返して、その場面でどのような考えが頭に浮かんでいたかを思い出してください。感情と同じようにいくつあっても問題ありません。
感情と同じように「確信度」を%として一緒に記入します。
例)
・こんなミスをするなんて私はダメな人間だ(90%)
・上司は私のことが嫌いなんだろう(80%)
自動思考を書いたら、その中から「Hotな自動思考」を選びます。
「Hotな自動思考」はその瞬間に一番あなたに影響を与えている自動思考のことです。
感情を見返して、%が高い感情を引き出す自動思考がどれかを考えると見つけやすいです。
「悲しみ」80%が一番高いとき、「Hotな自動思考」は「こんなミスをするなんて私はダメな人間だ」となるかもしれません。
4. 自動思考の根拠を書く
ここからが大切な作業です。まず、「Hotな自動思考」を肯定するような根拠を探します。
例)
・仕事のミスをした
・自分のミスによって、職場の人の仕事が遅れる
・上司に呼び出された
・資料の確認を忘れてしまった
などが挙げられます。
5. 自動思考の反証を書く
自動思考の根拠を書いたら、自動思考に対して「異議あり!」と反対するような事実を書き出します。
例)
・私は今まで上司にこれほど怒られたことはなかった
・期限を守って仕事をしてきた
・学生時代はレポートを丁寧に作成して、評価も良かった
・今までかかわったプロジェクトは結果的に成功していた
6. 適応的思考を書く
Hotな自動思考を決めて、根拠と反証を書いたら、適応的思考を書きます。
適応的思考は、自動思考+反証で骨組みを作成できます。
「こんなミスをするなんて私はダメな人間だ」+「しかし、私は期限を守って仕事をしてきたし、今までかかわったプロジェクトは成功していた」
例)
「ミスをして上司に怒られた。しかし、私は今まで期限を守って仕事をしてきたし、今までかかわったプロジェクトは成功していた。だから、私はダメな人間とは限らない」
とします。
適応的思考=ポジティブな考えというわけではありません。
自分を責めるのではなく、現実を踏まえた前向きな考えを言葉にする。それが適応的思考です。
7. 適応的思考を読んで気分の変化を確かめる
新しい考え方を持つことで、気分や行動にどんな変化があったかを振り返ります。
例)
・モヤモヤ(50%)
・悔しい(70%)
・悲しみ(80%)
・怒り(30%)
このように適応的思考を考えてから状況を振り返って感情に変化があるかを確かめます。
認知再構成法を誰とやるか?:一人でも、専門家とでも
認知再構成法は、自分ひとりで取り組むこともできますが、専門家と一緒に実践するとより効果的です。
支援者と一緒に認知際構成法に取り組む
認知行動療法に精通した専門家は、あなたの思考のパターンを理解しながら、的確な質問や視点の提示を通して「思考の検討」をサポートしてくれます。
また、認知行動療法を実施していなくても医師や心理師にセルフケアの本をやってみたいと相談して一緒に取り組むという選択肢もあります。
一方で、そもそも本当に認知再構成法を優先的にやるべきなのか、もっち違う方法が良いのではないか、など何に取り組みかを一緒に検討することも可能で高い治療効果が期待できます。
一人で認知際構成法に取り組む場合
書籍やワークブックを活用しながら、日常の中で思考記録表をつけて実践することも可能です。初めての方には、セルフヘルプに役立つノートやワークブックも出版されています。
「自分で始めてみたいけれど、どう書けばいいかわからない…」という方には、初心者にもわかりやすい構成大野裕先生の「心の晴れるノート」は、初心者でも取り組みやすく構成されています。
まとめ:考え方が変わると、人生が変わるかもしれない
認知再構成法は、私たちの心の働きをよりよく理解し、感情や行動のコントロールを取り戻すための大切な技法です。
- 自分の「考え」に気づく
- その「考え」を検証する
- 必要なら「考え」を見直す
このプロセスを通じて、落ち込みや不安といった苦しさを和らげ、前向きに問題と向き合う力が育っていきます。
もし「考え方のクセに苦しんでいる」「気分や行動が思うようにコントロールできない」という方は、ぜひ一度、認知再構成法を試してみてください。