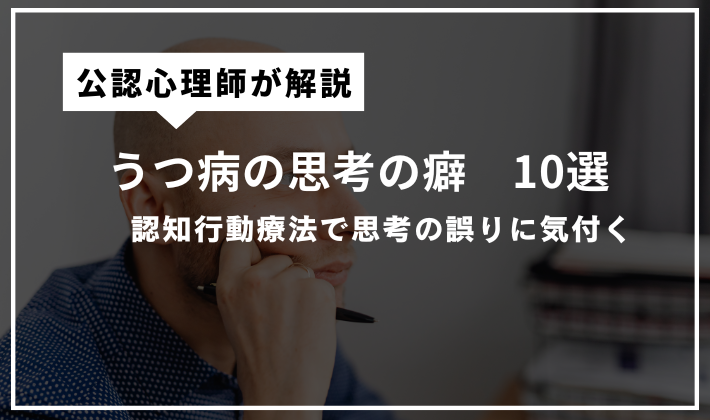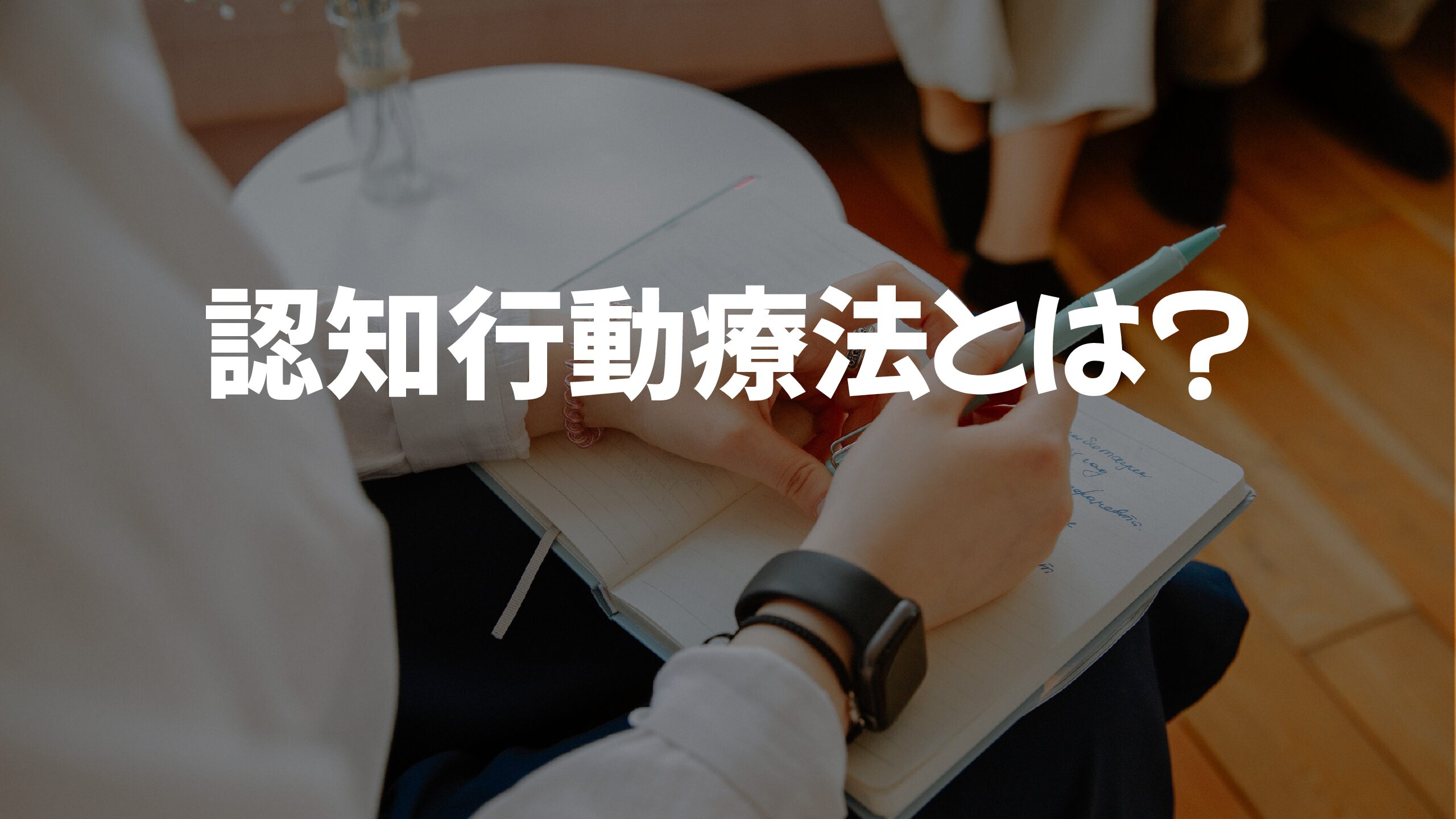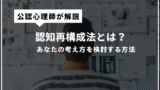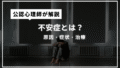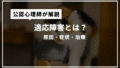こんにちは、公認心理師のだびでです。
みなさんは、何か失敗をしてしまった時や怒られた時に「私はダメな人間だ」「嫌われているに違いない」などネガティブな考えに頭が支配されてしまった経験はありませんか?
私たちは日々、さまざまな出来事に直面し、瞬時に判断を下しながら生活しています。その判断の背景には、私たちが無意識のうちに使っている「思考の癖」があります。
この思考のパターンは、脳が効率的に働くための仕組みであり、これまでの困難を乗り越えてきた「得意な考え方」でもあります。しかし、同じパターンばかりを使っていると、状況に合わない考えとなってしまい、時には自分を苦しめる原因になることもあります。
認知行動療法(CBT)では、気分を落ち込ませる思考のパターンを「認知の誤り」と呼びますが、これは決して「悪いもの」ではありません。大切なのは、自分の思考の癖に気づくことです。気づくことができれば、その考え方から少し距離を置いて、より柔軟に物事を見られるようになります。
今回は、認知行動療法の教科書ともいえる『認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで 第3版 -ジュディス・ベックの認知行動療法テキスト』を参考に、よくある10個の思考パターンを具体例とともにわかりやすく解説します。自分に当てはまるパターンを見つけて、思考の癖と上手につきあう第一歩を踏み出しましょう。
思考の癖とは何か?
私たちの心には、長い進化の過程で培われてきた「思考の癖」があります。
思考の癖は、私たちが生き延びるために発達してきた心の機能です。危険を素早く察知したり、複雑な状況を瞬時に判断したりするために、脳が効率的に働くための仕組みなのです。つまり、これまで困難を乗り越えてきた「得意な考え方」でもあります。
問題は、この思考の癖が「いつも同じパターンしか使えない」ことにあります。すべての状況に対して同じ考え方を適用してしまうと、かえって自分を苦しめてしまうことがあるのです。
そして、気分が落ち込んでいるときにある状況に直面すると現実的な考え方が難しくなって、思考の癖が「思考の誤り」となります。
認知行動療法では、「思考の誤り」を検討することで治療を目指します。ここで大切なのが「気づく」ことです。自分の思考パターンに気づくことができれば、その考え方から少し距離を置いて、より現実的に検討できるようになります。これが、思考の癖と上手につきあう第一歩なのです。
よくある10の思考パターン
今回は『認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで 第3版 -ジュディス・ベックの認知行動療法テキスト』で紹介されている10個のうつ病の方が陥りやすい認知の誤りを紹介します。
皆さんにも当てはまる思考の癖があるのではないでしょうか?
私なりにわかりやすい思考の名前も考えてみたので、イメージしやすい方で覚えていただければと思います。
1. 全か無か思考「白黒思考」
物事を「完璧な成功」か「完全な失敗」の二択で考えてしまう癖です。これはよく白黒思考とも呼ばれます。あいまいな考え(灰色)に耐えられず、「まあ、いいか」という柔軟な思考が難しくなってしまいます。
例)
「テストで90点を取ったけど100点じゃないからダメだ」
(一度ミスをした)→「自分は何をやってもうまくいかない」
この考えに囚われてしまうと、本当は十分合格点のはずなのに、完璧ではないから不合格だと感じて自分を苦しめてしまいます。
完璧と失敗の間にある「中間」(グレーゾーン)を意識的に見る習慣を持ち、「まあまあうまくいった」「ここはよかったけど、ここは改善できる」といった現実的な見方を探すことが大切です。
2. 破局視「バッドエンド思考」
何か悪いことが起きたときに「最悪の結果になる」と決めつけてしまう思考です。
現実的にありそうな可能性を考慮せず、未来をネガティブに予測してしまいます。ドラマやアニメは途中でだいたい悪いことが起こってそこからハッピーエンドに行きます。しかし、現実で悪いことが起きた時にそのままバッドエンドになると確信してしまうと気持ちが辛くなります。
例)
(上司から『話がある』と言われた)→「クビになるに違いない」
(友達からの返信が遅い)→「嫌われてしまった」
判断が早いことや最悪の結果をイメージしたうえで対策まで考えられる余裕があれば役に立つ考え方です。しかし、最悪の思考が出てきてあたかもそれを現実の出来事のように体験すると気分が落ちてしまいます。小さな出来事をいきなり「最悪の未来」に結びつけず、現実的にもっとありそうな可能性をいくつか考えることが大切です。
3. 過度の一般化「決めつけマスター」
一度や二度の失敗から「いつも失敗する」「何をやってもうまくいかない」と結論づけてしまう思考です。どのようなことも毎回起きているように感じてしまいます。その結果、限られた経験から「いつも」「必ず」「絶対」といった言葉で毎回起きているように考えてしまいます。
例)
一度プレゼンで失敗した→「自分はプレゼンを全くできない」
デートを断られた→「いつも私は誰からも愛されない」
本当に同じようなミスをしているならば、素早く同じような対策を行えるため、役に立つかもしれません。しかし、実は初めての失敗であったり、100回やって1回のミスである場合は、自信のなさにつながってしまいます。
「いつも」「絶対」などの言葉に注意し、事実として「いつも」失敗しているのかを振り返り、一つの出来事を全体に当てはめないことが大切です。
4. 心のフィルター「ポジティブブロック思考」
見えている世界と心の間に良いところが見えないフィルターをつけて、全体の中から悪いことだけを拾い上げてそれだけに注目する考え方です。
SNSで見たくない人やコンテンツをブロックして情報を遮断するように、心の中でポジティブな側面や肯定的な情報をブロックしてしまいます。
例
(10個の良い評価と1個の悪い評価をもらった)→「今回は悪かったんだ」
(評価の低いコメントがあった)→「自分はいい加減な仕事をしている」
ネガティブな要素だけを通すフィルターを外して全体のバランスを見て、ポジティブな要素も視野に入れることが大切です。
5. ポジティブな側面の否定・割引(ポジティブ100%オフ思考)
良いことが起きても「それは大したことじゃない」と打ち消し、ポジティブな体験、成功、長所などを無視するか割り引いて考える考え方です。
頭の中で店員さんが「いまならポジティブな側面は100%オフです」と言っているような考え方です。
なんて嬉しくないサービスでしょうか。
ポジティブブロック思考と似ていますが、ポジティブブロック思考はポジティブな事実をブロックして、最初から良いものが見えていない考え方です。一方で、ポジティブ100%オフ思考は、良いものは見えているけれど、ポジティブな事実を「本物じゃない」と値札を書き換えてしまい、事実として見ようとしない考え方です。
例)
プロジェクトは成功した→「運が良かっただけ」
褒められた→「お世辞で言っているだけ」
成功体験や物事の終わりに反省点を見つけることは成長の過程で必要です。しかし、自分の成果や長所を正当に評価し、自分の貢献を認めることも非常に大切です。
6. ねばならない思考「ルールでガチガチ思考」
「こうあるべきだ」という固定的で厳格な理想を自分や他人に課す考え方です。
このルールが守れないと「失格」だと感じ、罪悪感や怒りを感じやすくなります。自分に対して厳しすぎるルールは自己批判につながり、他人に対して厳しすぎるルールは怒りやイライラにつながります。
例)
「少しのミスもするべきではない」
「いつも完璧でなければならない」
完璧でなくても大丈夫という許可を自分に与え、人間は完璧ではなく時にはミスをすることもあると認めることが大切です。
7. 読心術(メンタリスト思考)
他人の考えていることを証拠もなく決めつけてしまい、他人の考えが自分にわかると信じ込む考え方です。
某メンタリストみたいに相手の心を読もうとしますが、情報を集めずにネガティブな方向で相手の心を読んでしまいます。
例)
(上司が難しい顔をしている)→「理解していないと思っている」
(友達が静かだ)→「私のことを嫌っているに違いない」
相手がどう感じているのかを考えることは対人関係では重要です。しかし、ネガティブメンタリストになると対人関係がうまくいかなくなって気分も落ち込んでしまいます。
相手に直接確認する、他の可能性(相手が疲れている、別のことで悩んでいるなど)を考えてみることが大切です。
8. 個人化(悲劇の主人公思考)
自分に関係のないことまで「自分のせいだ」と思い込み、他人の行動や出来事の原因を合理的な根拠なく自分に結びつける考え方です。どんなことが起きても「全部私のせいだ」と考えて自分を責めてしまいます。
映画や小説、アニメで「俺のせいだ」「私のせいだ」と自分を責めるシーンがありますよね。悲劇の主人公のように、本当は自分のせいだけではないのに、「全部自分のせい」だと考えてしまいます。
例)
(近所の人が挨拶をしなかった)→「私が何か気に障ることをした」
(プロジェクトが失敗した)→「全部自分の責任だ」
すべてを人のせいにしないで、自分の責任を認めること自体は素晴らしいことです。しかし、過度に「私のせい」にすると責任でつぶれてしまいます。自分がコントロールできる範囲を見極め、他の要因がないか考えることが大切です。
9. 感情的理由づけ「真実はいつも1つ思考」
自分の感情を根拠にして「これが事実だ」と決めつけ、「そう感じる」ことを証拠に事実だと思い込む考え方です。
某アニメの主人公は事実をかき集めてから推理して「真実はいつも一つ」と言っています。しかし、根拠を自分の感情で決めてしまうのです。
例)
(仕事はうまくいっているが、無能だと感じる)→「だから私は仕事ができない」
(周りが楽しそうに話している感じる)→「自分は嫌われている」
感情はすごく大切ですし、あなたがそのように感じていることは事実です。しかし、「そう感じる」からといってその気持ちが出てきた状況への解釈が真実とは限らないため、客観的な事実を確認することが大切です。
10. トンネル視「盲目思考」
悪いことしか目に入らなくなり、状況においてネガティブな側面しか見えず、ポジティブな側面が完全に視界から消える考え方です。
よく「恋は盲目」といいますよね。好きな人ができるとその人の良いところしか見えなくなってしまう。1日がいい日だったか、悪い日だったかは好きな人と話せたかで決まります。
トンネル視もそのような感じです。悪いこと、嫌なことしか目に入らず、全てが「ダメだった」と感じることがあります。
特定の出来事ではなく、1日全体・状況全体に対する認識の歪みです。
例)
「今日は全くひどい1日だった」と考える
実際には「着替えられた」、「散歩に出かけた」、「友人と話した」など良いこともあった。
トンネルから出て視野を広げて全体を見て、どんな日にも良いことと悪いことが混在していることを思い出すことが大切です。
思考パターンに気づいたら、どうする?
自分の思考の癖に気づくことが変化の第一歩です。気づくことで、落ち込みのパターンから抜け出し、考え方の選択肢を広げることができます。
もっと丁寧に考え方を検討する方法として認知再構成法があります。
ステップ1:自分の「思考の癖」にラベルを貼る
ネガティブな気持ちになったら、どのような考えが頭の中にあるのかをメモします。その思考が10個のうちどれに当てはまるかを考えて名前をつけましょう。名前をつけることで、思考と自分を切り離すことができ、客観的に眺められるようになります。
ここでは「思考の癖」を見つけることが大切なので、2つ以上のエピソードを集めることが重要です。
ステップ2:その思考を一歩引いて眺める
「この考え方は事実か?他の見方はないか?」を検討します。例えば、トンネル視(うつは盲目思考)であれば、本当は良かったこと、一日の中でポジティブなことはなかったかを探してみます。
一つの見方に固執せず、複数の角度から状況を見ることで、思考の幅が広がります。
ステップ3:より現実的・柔軟な見方を探す
CBTでは「適応的思考」と呼ばれるものです。完全にポジティブでなくても、よりバランスの取れた見方を探していきましょう。
すぐに思考を変える必要はありません。まずは「気づく」ことが大切な第一歩です。気づくだけでも、自動的な思考パターンから距離を置けるようになります。気づきの積み重ねが、自然と考え方の柔軟性を高め、落ち込みにくい思考習慣につながります。
まとめ
思考の癖は決して悪いものではありません。問題なのは、出来事の内容に関係なく、その思考パターンしか使えなくなってしまうことです。
そして、思考の癖が柔軟性を失うと「思考の誤り」になってしまいます。思考の誤りは現実を歪めて捉えさせ、不必要な苦しみや誤った判断を生み出す危険性があります。
自分の思考の癖に気づくことで、思考と距離を置けるようになります。まずは日常で思考パターンに気づく練習をしてみましょう。
より詳しく学びたい方には認知行動療法(CBT)の書籍やワークブックがおすすめです。また、専門家(公認心理師・臨床心理士)のカウンセリングも選択肢の一つです。セルフヘルプでも効果はありますが、困難な場合は専門家のサポートを検討してみてください。