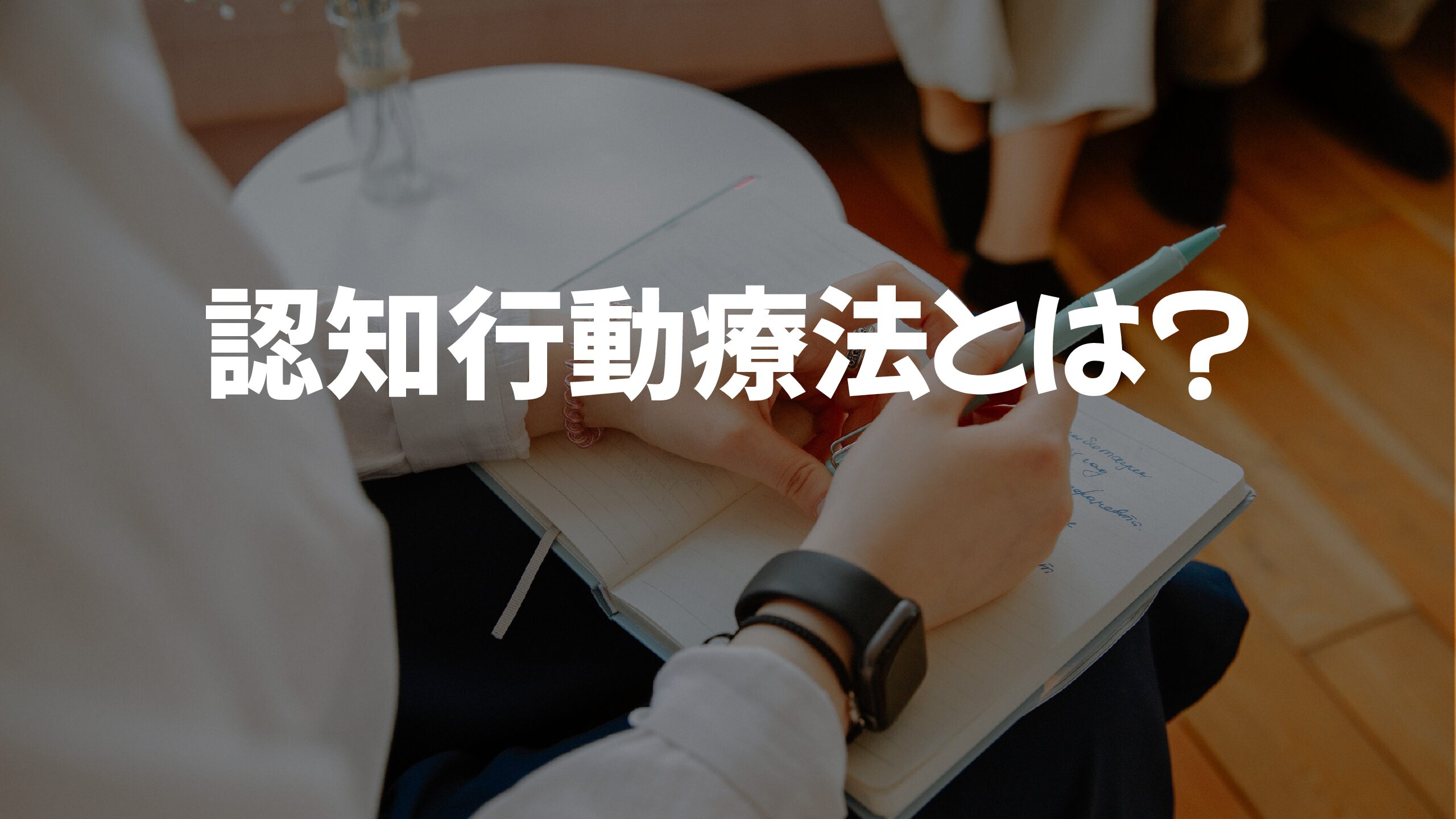こんにちは、公認心理師のだびでです。
今回は、発達障害のひとつである「自閉スペクトラム症(ASD)」について、その特徴や支援の方法をわかりやすくお伝えします。
「うちの子、ちょっと個性的かも?」「集団行動が苦手みたい」
そんな不安を感じている保護者の方や、周囲の子どもたちの理解を深めたい方へ。このブログを通して、ASDへの理解が深まり、新たな「気づき」に繋がればうれしいです。
自閉スペクトラム症とは
自閉スペクトラム症(ASD:Autism Spectrum Disorder)は、コミュニケーションやこだわり行動などの面に特性が見られる発達障害のひとつです。
「スペクトラム(連続体)」という言葉の通り、そのあらわれ方は人によって異なり、軽度から重度までグラデーションがあります。今回は、主に子どものASDに見られる特徴を中心に解説します。
ASDの診断基準(DSM-5より)
ASDは正式な診断名であり、診断には主に以下の2つの領域での特性が確認される必要があります
A. 社会的コミュニケーションと対人関係の困難
以下のすべてに当てはまる傾向があります
- 相手との気持ちのやりとり(情緒的相互関係)が難しい
- 視線や表情など、言葉以外を使ったコミュニケーションが苦手
- 年齢相応の対人関係を築いたり、維持したりすることが難しい
B. 興味や行動の偏り
以下のうち少なくとも2つが見られます。
- 同じ行動や言葉を繰り返す
- 決まったやり方へのこだわり
- 非常に狭く強い興味をもつ
- 感覚への敏感さ・鈍感さ
ASDの子どもによく見られる4つの特徴
診断基準をもう少し噛み砕いて、日常よく見られる4つの特徴について説明します。
1.人との関わり方が独特で難しい
ASDの子どもは、「どうやって相手と関わればいいのか」が直感的にわかりにくいことがあります。
- 一人遊びを好む(ごっこ遊びや集団遊びに入りにくい)
- 目が合いにくい、または合わせるタイミングが合わない
- ケガをした友達にどう声をかけていいかわからない(共感の示し方が独特)
- 冗談や皮肉を言葉通りに受け取ってしまう
集団生活の暗黙のルールがわからず、幼稚園や学校で戸惑ってしまうことも少なくありません。
2.言葉やコミュニケーションの使い方が独特
ASDの子どもは、言葉の成長がゆっくりだったり、少し変わった使い方をすることがあります。
- オウム返しをする(反響言語:聞いた言葉をそのまま繰り返す)
- 「あなた」「○○ちゃん」などの使い分けが難しい(代名詞の逆転)
- 一方的に自分の話したいことを話し続けてしまう
- 「足が棒になる」などの比喩や冗談が通じにくい
- 指さしやジェスチャー(手振り・表情)で意思疎通が苦手
言葉をたくさん知っていても、それを「会話のキャッチボール」として使うことに難しさを感じることがあります。
3.こだわりが強く、同じことを繰り返す
ASDの子どもは、「いつも同じ」であることに安心感を覚えたり、特定のことに強く熱中したりします。
- いつも同じ道を通らないと不安になる
- 家具の配置や予定が急に変わるとパニックになる
- 手をひらひらさせる、ジャンプを繰り返すなどの独特な動き
- 特定のもの(ひも、ゴミ箱、数字など)に強い関心を示す
一見不思議に見える行動も、本人にとっては「安心感を得るための大切な行動」である場合が多いのです。
4.感覚の敏感さ・鈍感さ
まわりの子どもが気にならない刺激に強く反応したり、逆に無反応であったりすることがあります。
- 聴覚過敏:掃除機の音や運動会のピストル音が苦手
- 触覚過敏:服のタグや特定の布の感触を嫌がる
- 鈍感さ:転んでも痛みに気づきにくい、暑さ寒さに鈍感
- 偏食:味や舌触りへのこだわりが強い
「わがまま」ではなく、脳の特性として刺激を強く受け取りすぎている(または受け取りにくい)状態です。
ASDの子どもへの支援:生きづらさを減らすために
ASDの子どもたちは、その特性ゆえに「わかってもらえない」「うまくいかない」という生きづらさを感じやすいです。しかし、適切な環境と支援があれば、安心して過ごすことができます。
療育(りょういく)によるサポート
療育は、児童発達支援センターや放課後等デイサービスなどで受けられます。 例えば、**「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」**では、ゲームや遊びを通して、「貸して」「いいよ」「ごめんね」といった人とのやりとりや、感情のコントロールを楽しく学びます。
環境調整(TEACCHなどの視点)
ASDの子どもには、言葉だけで伝えるよりも「見てわかる」工夫が効果的です。これは**TEACCH(ティーチ)**という支援法の考え方にも通じます。
- 予定の見える化:1日のスケジュールを絵や写真で張り出す
- 場所の構造化:「勉強する場所」「遊ぶ場所」を家具などで区切る
- クールダウンスペース:感覚過敏がある場合、静かで暗い場所を用意する
「頑張らせる」のではなく、「環境を変えて、できやすくする」ことが大切です。
薬物療法について
ASDそのものを治す薬はありませんが、「眠れない」「不安が強すぎてパニックになる」「イライラが止まらない」などの二次的な困りごとには、お薬が助けになることがあります。医師と相談しながら、お子さんの生活の質(QOL)を上げるための選択肢のひとつとして考えます。
「もしかしてASDかも」と思ったら
このブログを読んで、「うちの子に当てはまる気がする」「私自身もそうかもしれない」と感じた方もいるかもしれません。
発達障害の“特性”は、実は誰にでも少しずつあるものです。また、困りごとの原因がASDではなく、愛着の問題や環境の変化である可能性もあります。
一人で抱え込まず、ぜひ専門家(地域の保健センター、児童発達支援センター、精神科など)にご相談ください。診断は「レッテル」ではなく、適切な支援を受けるための「パスポート」になります。
最後に
ASDは親の育て方のせいでも、本人の努力不足でもありません。生まれ持った脳の機能のタイプです。
ASDの子どもたちは「ちがい」があるだけで、「間違い」ではありません。
「発達障害」と呼ばれるのは、今の社会の枠組みに少し合わない部分があるから。もしその枠が広がれば、それは障害ではなくなるかもしれません。適切な支援と理解があれば、ASDの子どもたちはその独自の感性や集中力といった「強み」を活かして、のびのびと生きていけます。
イチロー選手や米津玄師さん、スティーブ・ジョブズ氏のように、特性を強みに変えて社会に大きく貢献する人もたくさんいます。 心理師として、一人の支援者として、すべての子どもたちが自分らしく輝ける未来を信じています。
参考文献
- 岡田 俊. (2017). 自閉スペクトラム症 (ASD) の特性理解. 心身医学, 57(1), 19–26.
- American Psychiatric Association. (2023). DSM-5-TR 精神疾患の分類と診断の手引 (日本精神神経学会 監修; 高橋三郎 ほか 監訳). 医学書院. (原著出版年: 2022)
- 榊原洋一 (監修). (2017). 最新図解 自閉症スペクトラムの子どもたちをサポートする本. ナツメ社.