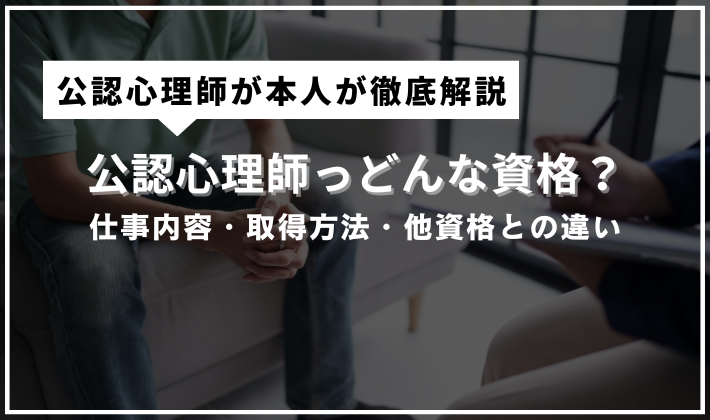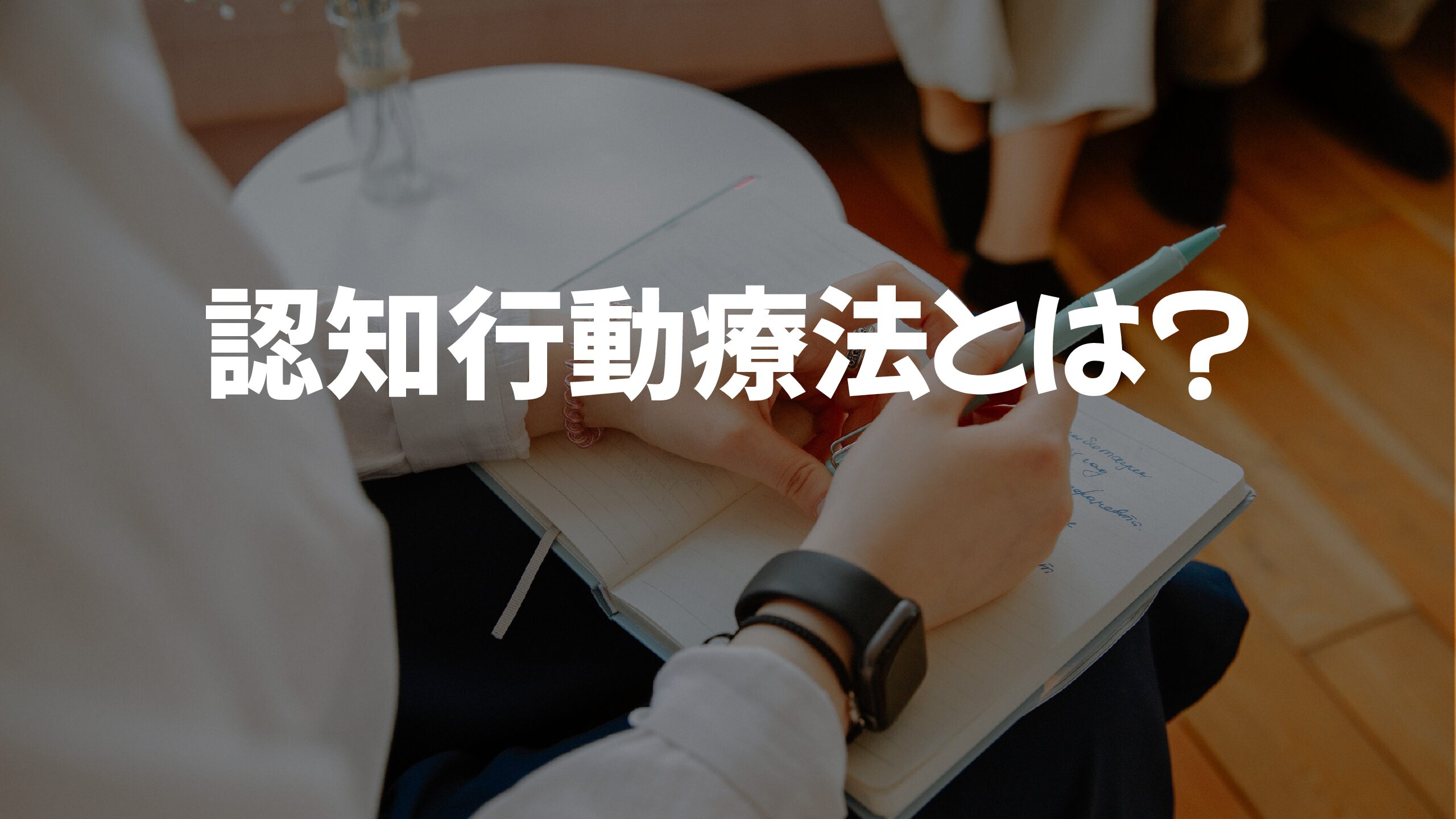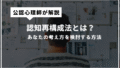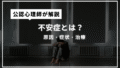「カウンセリングを受けたいけど、どの資格の人に相談すればいい?」「公認心理師って聞いたことあるけど、他の心理士、〇〇カウンセラーとは何が違うの?」
心の健康に関する悩みを抱えたとき、こんな疑問を感じたことはありませんか?また、心理職を目指している高校生や大学生の方の中には、「公認心理師ってどんな資格なんだろう」「どうやったらなれるのかな」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
実は、公認心理師は2017年に誕生したばかりの、心理職では唯一の国家資格です。これまで心理カウンセラーには様々な民間資格がありましたが、国が正式に認めた資格はこの公認心理師が初めてなのです。
なので、知らない方がいないのも当然です。今回のブログをきっかけに知っていただれば嬉しいです。
このブログでは、公認心理師がどのような資格なのか、どうすれば取得できるのか、そして実際にどんな場所でどんな仕事をしているのかを、現役の公認心理師である私がわかりやすく解説します。
公認心理師とは
公認心理師は、2017年に施行された「公認心理師法」に基づく国家資格です。心理学の専門知識と技術を用いて、心の健康に関する支援を行う専門家として、国が正式に認定しています。
これまで日本には、臨床心理士をはじめとする様々な心理系の資格がありましたが、すべて民間資格でした。そのため、個人に専門性があったとしても働き方に限界もありました。
そこで、心の健康を支える専門家の質を保証し、国民が安心して相談できる環境を整えるために、公認心理師という国家資格が創設されたのです。
公認心理師の大きな特徴は、医療・教育・福祉・司法・産業という5つの領域で幅広く活躍できる点です。また、法律によって業務内容が明確に定められているため、専門性と信頼性が担保されています。
公認心理師の資格を取る方法
一般的なルートとしては、公認心理師になるには、大学と大学院で合計6年間、心理学を専門的に学ぶ必要があります。これは、高い専門性を持った心理職を育成するための制度設計です。
具体的なルートは以下の通りです。
標準的なルート
公認心理師を目指す多くの方は、大学+大学院で6年間学ぶルートを選択する方が多いです。
- 大学(4年間):文部科学大臣・厚生労働大臣が指定する科目を履修します。心理学の基礎理論、心理検査、カウンセリング技法、精神医学、発達心理学など、幅広い知識を学びます。また、実際に公認心理師が働いている5領域の機関に実習へ行きます。
- 大学院(2年間):公認心理師を取るために指定された大学院に入る必要があります。文部科学大臣・厚生労働大臣が指定する科目を履修します。より専門的な実習や研究を行います。実際の医療機関や教育現場で、スーパービジョン(指導)を受けながら実践的な経験を積みます。
- 国家試験の受験:年に1回(3月頃)実施される公認心理師国家試験に合格する必要があります。
その他のルート
大学卒業後、指定された施設で2年以上の実務経験を積むことでも受験資格が得られます
詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。
このように、公認心理師になるためには長い学習期間と実践経験が求められます。それだけ、人の心に関係する仕事の責任が重く、高い専門性を身につけた人が公認心理師になることができます。
公認心理師の仕事
公認心理師は、法律で定められた4つの役割があります。
また、実際に公認心理師が働く領域は大きく分けて5つに別れています。法律で定められている仕事
公認心理師法で定められている4つの役割
公認心理師法第2条では、公認心理師の業務を以下のように定義しています。
(目的)
第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
公認心理師法(◆平成27年09月16日法律第68号)
1.心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
心理検査や面接を通じて、相談者の心の状態を正確に把握します。
例えば、知能検査や人格検査を実施し、その人の特性や困りごとの背景を分析します。この結果が支援に活用されます。
2.心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
各領域によって時間や目的は少し異なりますが、いわゆるカウンセリングです。
相談者の悩みに耳を傾け、臨床心理学的な知見に基づいて適切な助言や支援を行います。認知行動療法などの専門的な技法を用いるかかわりも求められます。
3.心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
本人だけでなく、家族や学校の先生、職場の上司など、関係者への支援も重要な業務です。例えば、子どもの発達に悩む保護者に対して、関わり方のアドバイスや発達障害の説明などを行います。
4.心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
地域や学校で、メンタルヘルスに関する講演会や研修を行うことも求められています。実際、すべての公認心理師がこのような活動をしている訳ではありませんが、予防的な観点から、広く心の健康に関する知識を伝える役割も担っています。
実際の仕事(5領域)
次に、公認心理師は、以下の5つの領域で幅広く活躍しています。
- 保健医療領域
- 教育領域
- 産業・労働領域
- 司法・犯罪領域
- 福祉領域
1. 保健医療領域
病院やクリニックで、精神疾患や心身症を抱える患者さんへのカウンセリング、心理検査などを行います。うつ病、不安症、統合失調症などの治療において、医師や看護師と連携しながら心理的支援を提供します。
公認心理師は、精神科だけでなく、総合病院の身体科などでも活躍しています。医師、看護師、薬剤師、リハビリテーション職などと協力し、多職種カンファレンスに参加することで、患者さんを「医療を利用する生活主体」として捉えた包括的な支援を提供します。
また、心理検査など保険点数を取ることができることが他の資格と大きく異なります。これらの業務を行う際、公認心理師は主治医との連携が法律で義務付けられています。特に医療現場では、医師の指示のもとで業務を行うことが求められ、多職種連携(チーム医療)の一員として活動します。
2. 教育領域
最もイメージしやすいのは、スクールカウンセラー(SC)としての役割ではないでしょうか。学校現場において、公認心理師はいじめ問題、不登校、学習面での困難、友人関係のトラブル、発達上の悩みなど、さまざまな課題を抱える子どもたち一人ひとりに寄り添い、個別のカウンセリングや心理的支援を提供しています。
また、子どもたちだけでなく、子育てや子どもの問題に悩む保護者に対しても相談支援を行い、さらには日々子どもたちと接する教員に対しても専門的な助言や心理教育を実施しています。
SCの役割は、個別面接に留まらず、コンサルテーション(教職員や保護者へのアドバイス)、カンファレンス(関係者による支援会議)、危機対応(事件・事故発生時の心理的支援)など、学校システム全体への介入を行うこともあります。
加えて、教育委員会や各地域に設置されている教育相談センターといった教育行政機関においても、教育現場で生じるさまざまな心理的な課題の解決に向けて、専門的な立場から積極的に取り組んでいます。
3. 福祉領域
公認心理師は、児童相談所、放課後等デイサービス、高齢者施設、障害者支援施設をはじめとするさまざまな福祉施設において活躍しています。
児童相談所では、虐待を受けた子どもたちへの心理的ケアや、どもの言葉にならないメッセージを心理的に受け止め、適切な支援へとつなげる役割を担っています。また、発達障害のある方々への支援、認知症の高齢者やそのご家族への心理的サポートなど、福祉的な支援を必要とする幅広い対象者に対して、専門的な心理支援を提供しています。
福祉領域では、個人への直接支援だけでなく、地域援助や予防活動も重視されています。地域住民が気軽に利用できるサービス・システムの構築や、地域の社会資源へのコンサルテーション活動を通じて、間接的な支援も行います。
4. 司法・犯罪領域
家庭裁判所、少年鑑別所、刑務所、保護観察所などの司法・矯正施設において、公認心理師は非行を起こした少年たちや罪を犯した人々に対する更生支援を行っています。
具体的には、心理的査定(アセスメント)を通じて、対象者のパーソナリティ特性や非行・犯罪に至った動機を分析し、家庭裁判所の審判や矯正施設における処遇計画の立案に貢献します。また、認知行動療法を基盤とした再犯防止プログラムの実施も重要な業務です。
さらに、犯罪や事件の被害を受けた方々への心理的サポート(トラウマケア、二次被害の防止)も担っており、多岐にわたる専門的な心理支援業務に携わっています。
5. 産業・労働領域
企業の健康管理室や産業カウンセリングルームなどに所属し、従業員のメンタルヘルス支援に幅広く取り組んでいます。
具体的には、個別カウンセリングを通じた心理的サポート、法律で義務付けられたストレスチェックの実施と結果の分析、そして休職した従業員の職場復帰支援プログラムの運営などを行っています。働く人々の心の健康を守り、職場環境の改善に貢献するという重要な役割を担っています。
また、管理職や一般従業員を対象とした企業研修においてメンタルヘルスに関する知識や対処法について講義を行ったり、ストレス予防やハラスメント防止といったメンタルヘルス予防のための組織的な取り組みにも積極的に関わっています。
近年は、キャリア形成支援のニーズも高まっており、人生の転機における悩み相談や仕事選びに関するアドバイスなど、疾病治療だけでなく予防と生産性向上にも貢献しています。主な連携職種は、企業医師(産業医)、産業保健師、キャリアコンサルタントなどです。
名称独占資格としての公認心理師
公認心理師の大きな特徴として名称独占資格であることが挙げられます。これは、資格を持っていない人が「心理師」という名称を使用することが法律で禁止されているということを意味します。公認心理師が「公認心理士」と書いてある書類を見つけると指摘してくるので気を付けましょう(正式名称に修正する必要があるのでしょうがないんです…。)
無資格者が「心理師」を名乗ることは違法行為となり、罰則の対象となります。これにより、利用者は「公認心理師」という肩書きを見れば、その人が国が認めた専門的な教育と訓練を受けた心理職であることを確実に判断できます。心理支援を受ける際の安心材料となる重要な仕組みです。
主要な心理系資格との比較
心理系の資格にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。代表的な資格のいくつかと比較してみましょう。
| 資格名 | 資格の種類 | 認定団体 | 主な活動場所 | どうやって取るか | 医師との連携 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公認心理師 | 国家資格 | 国(文部科学省・厚生労働省) | 病院、学校、福祉施設、裁判所、企業など幅広い | 大学4年+大学院2年+国家試験に合格 | 必要 |
| 臨床心理士 | 民間資格 | 日本臨床心理士資格認定協会 | 病院、学校、福祉施設など | 指定の大学院を卒業+資格試験に合格 | 特になし |
| 産業カウンセラー | 民間資格 | 日本産業カウンセラー協会 | 企業の相談室など | 協会の講座を受講+試験に合格 | 特になし |
| 認定心理士 | 民間資格 | 日本心理学会 | 特定の職場に限らない(心理学の基礎を学んだ証明) | 大学で指定の科目を履修 | 特になし |
臨床心理士との関係
公認心理師は「臨床心理士」とよく比較されます。臨床心理士は長い歴史があり、現場で信頼されている民間資格です。実際、多くの公認心理師が臨床心理士の資格も持っています(両方持つことを「ダブルライセンス」と言います)。
「どちらの資格の方がすごいのか?」という議論もありますが、資格だけで専門性の高さを比べることはできません。
公認心理師が他の資格より優れているわけではありませんが、国家資格であるため、社会的に信用されやすいという特徴があります。
まとめ
公認心理師は心理職で唯一の国家資格です。この資格を取得するには、大学4年間と大学院2年間の合計6年間、心理学を専門的に学び、その後国家試験に合格する必要があります。資格を取得した公認心理師は、国民に対して心理的な分析、支援、助言、教育を行うことが主な仕事です。
活動できる場所は、保健医療領域、教育領域、産業・労働領域、司法・犯罪領域、福祉領域の5つの領域に広がっており、子どもからお年寄りまで、あらゆる年代の心の健康をサポートする仕事です。まだ新しい国家資格であることも含めてさまざまな課題があります。しかし、法律で定められた専門性の高い資格なので、これから公的機関や病院で心理職として働くなら、公認心理師の資格が基本になっていくでしょう。
もしあなたが心理職を目指しているなら、公認心理師の取得を検討してみてください。また、カウンセリングを受けたいとお考えの方は、カウンセラーがどんな資格を持っているかを選ぶときの参考にしてみるとよいでしょう。