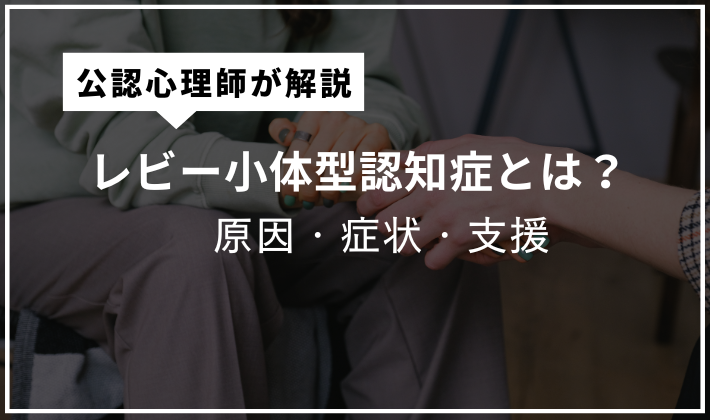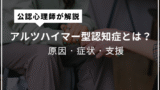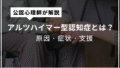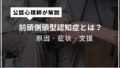皆さん、こんにちは!公認心理師のだびでです。
日本では高齢化が進み、認知症の方が増えています。認知症にはいろいろな種類があり、それぞれ症状が違います。適切に支援するには、それぞれの認知症の特徴を理解することがとても大切です。
今回は、認知症全体の約10~20%を占める「レビー小体型認知症(DLB)」について解説します。この病気は幻視(実際にないものが見える)、パーキンソン症状(体が動きにくくなる)、認知機能の波(調子の良い時と悪い時がある)など、アルツハイマー型認知症とは違う特徴があります。正しい知識を持つことで、本人や家族が生活しやすくなります。
レビー小体型認知症の原因
レビー小体型認知症(DLB)は、脳内に「レビー小体」という特殊なタンパク質(α-シヌクレイン)がたまることで起こる病気です。このレビー小体が大脳皮質や脳幹に広がり、神経細胞の働きを妨げることでさまざまな症状が出てきます。
レビー小体がたまると、特に脳内の「アセチルコリン」や「ドパミン」という物質を使う神経系に大きな影響を与えます。これにより、記憶や注意力、体の動きをコントロールする神経伝達物質のバランスが崩れ、認知機能の低下や体が動きにくくなるなどの症状が現れます。
レビー小体型認知症の主な症状
レビー小体型認知症は、次の4つの主な特徴を持つが特徴です。
- 認知機能の変動
- 幻視
- REM睡眠行動障害(RBD)
- パーキンソニズム
これらの中核症状について、具体的に見ていきましょう。
認知機能の変動(変動性認知障害)
レビー小体型認知症に特徴的な症状として、認知機能、注意力、覚醒状態が一日のうちでも突然変動することがあります。これは、せん妄様の変動として現れ、しっかりと会話できる時間と反応が乏しくぼんやりする時間が交互に現れます。
この変動により、家族が「認知症が治ったのではないか」と期待するほどしっかりしている時間もあれば、数時間後には全く反応が乏しくなることもあります。
幻視
多くのレビー小体型認知症の方に現れる代表的な症状です。幻視の内容は人や小動物、虫などが多く、本人には実在するかのように見えることが特徴です。
また、一般的に幻視とは何もないところに何かが見えることを指しますが、レビー小体型認知症の幻視は、実際にあるものが全く別のものに見える「パレイドリア」が特徴的です。
たとえば、
- カーテンがワンピースを着ている女性に見える
- 壁の汚れが虫に見える
- 庭に咲いている赤い花が赤い服を着ている女の子に見える
本人にとって幻視は非常にリアルであるため、周りからみたら妄想のように見えることもあります。
パーキンソン症状
レビー小体型認知症の多くの方が経過の中で発症する重要な症状です。レビー小体型認知症に特徴的なパーキンソン症状には以下があります:
- 筋固縮:筋肉が固くなり動かしにくくなる
- 寡動:動きが少なく小さく、そしてゆっくりになる
- 姿勢反射障害:姿勢のバランスが上手く保てない
さらに、パーキンソン症状が進行すると以下の症状が現れることがあります。
- ちょこちょこ歩くような小刻み歩行
- 足がすくんだり、突然止まってしまうすくみ足
- 前傾姿勢
などの特徴が見られます。
レム睡眠行動異常症(RBD)
レム睡眠行動異常症とは、大きな寝言、腕や脚をばたつかせるような激しい動きなど、レム睡眠中に起こる異常な行動を指します。
レム睡眠とは、眠っている間にまぶたの下で目が動き、脳が活発になって鮮明な夢を見る時間のことです。普通はこの時、体は大きく動きませんが、レビー小体型認知症の方は夢の内容を実際に体で演じてしまうことがあります。
レム睡眠行動異常症はレビー小体型認知症と診断される10~20年前から見られることもあり、中心的な症状として重視されています。
レビー小体型認知症の治療とケア
薬物療法
現在、レビー小体型認知症を完全に治療する薬はありません。ドネペジル(アリセプト)といった症状の軽減、進行を遅らせる効果が期待される薬が一応はあるという状態です。絶賛研究中といった感じですね。
幻視に対しては、まずコリンエステラーゼ阻害薬を試みることが推奨されます。抗精神病薬への薬剤過敏性があるため、必要時にはクエチアピンやクロザピンなど副作用の少ない非定型薬を慎重に使用します。
また、パーキンソン症状に対しては抗パーキンソン薬(レボドパ)を使用しますが、幻視・妄想を悪化させる可能性があるため、最小限の投与にとどめ徐々に増量します。
レム睡眠行動異常症に対してはメラトニンやクロナゼパムが用いられます。
環境調整
日常生活では、レビー小体型認知症の方が安心して過ごせるように生活する範囲の環境をと問えたり、周囲の人の接し方を工夫することが重要です。
幻視への対応:幻視を否定せずに受け止め、本人が脳の誤作動として見えていることを理解することが大切です。不安時には寄り添って安心感を与え、室内の照明調整や落ち着いた環境設定も効果的です。
認知機能変動への対応:一貫性のある日課の確保や静かな環境の維持が重要です。また、刺激を減らして患者を混乱させない工夫を行いましょう。
パーキンソン症状への対応:理学療法や作業療法によるバランス訓練・筋力増強を行い、必要に応じて歩行補助具を使用します。家屋内の手すり設置などで転倒防止策を講じ、起立性低血圧にも注意が必要です。
レム睡眠行動異常症への対応:寝室に硬い物や鋭利な物を置かず、ベッド柵やマットレスで転落・衝突を防ぎます。また、睡眠前の興奮刺激を避けることも大切です。
公認心理師の役割
現在、私たち公認心理師は認知症の方に直接関わる機会があまり多くありません。これは今後の支援の形として検討するべき課題です。
今のところ、公認心理師の主な役割は、認知症の検査と家族などへのサポートが中心となっています。
神経心理学検査
DLBの診断や認知症の程度を評価するために認知機能検査を実施します。検査結果から本人の認知機能プロフィールを把握し、個別の支援計画立案に活用します。
認知症の中でもどの型であるかなどの情報の1つとして必要になる場合があります。
DLBの診断や症状評価には、以下の心理検査が用いられます:
- **HDS-R、MMSE:**認知機能を測定するためによく使われる神経心理学検査です。
- FAB:簡易的ですが、前頭葉機能を中心に測定した検査です。
- ノイズパレイドリアテスト:レビー小体型認知症特有の幻視であるパレイドリアを評価する検査です。
- 時計描画テスト(CDT):時計を描いてもらうことで認知機能を測定します。
本人・家族支援
心理検査の結果を分析し、その方の認知機能に合わせた日常生活の工夫を具体的に提案します。
また、医師や看護師、作業療法士、ケアマネジャーなどの専門家と協力して、総合的な支援計画を作ります。さらに、検査結果から認知症の方が「できること」や「得意なこと」を見つけ出し、それを活かせる環境づくりも提案します。
認知症の家族を介護する方の心の負担はとても大きく、「介護うつ」や「燃え尽き症候群」になってしまうことも少なくありません。そのため、家族へのサポートとして、ストレスの対処法や効果的な接し方をアドバイスしたり、気持ちを整理するためのカウンセリングを行ったりします。また、同じ悩みを持つ方々が集まる「家族会」を紹介したり、今後の見通しについての情報を提供したりすることも公認心理師の大切な役割です。
まとめ
レビー小体型認知症は、幻視や認知機能の変動、パーキンソン症状といった独特な症状を示す疾患です。アルツハイマー型認知症とは異なる病態と症状の特徴を理解することで、より適切な支援が可能になります。特に幻視は、周囲の人が理解していなければ本人が何をしているかわからずに家族だとしても否定的な見方をしてしまうこともあります。
最も重要なのは、症状の背景にある病気の仕組みを理解し、本人の困りごとに寄り添うことです。DLBの方は「困った人」ではなく「困っている人」なのです。幻視が見えていても、それは本人にとってリアルな体験であり、否定するのではなく受け止めることが大切です。適切な理解と支援により、レビー小体型認知症の方を含む高齢者も安心して生活できる環境を一緒に作っていくことが、これからの社会には必要なことです。
主要参考文献
黒川由紀子・扇澤史子(編)(2018)『認知症の心理アセスメント はじめの一歩』医学書院
河野和彦. (2016). ぜんぶわかる認知症の事典: 4大認知症をわかりやすくビジュアル解説. 成美堂出版
川畑智 (2021). マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界. 文響社.