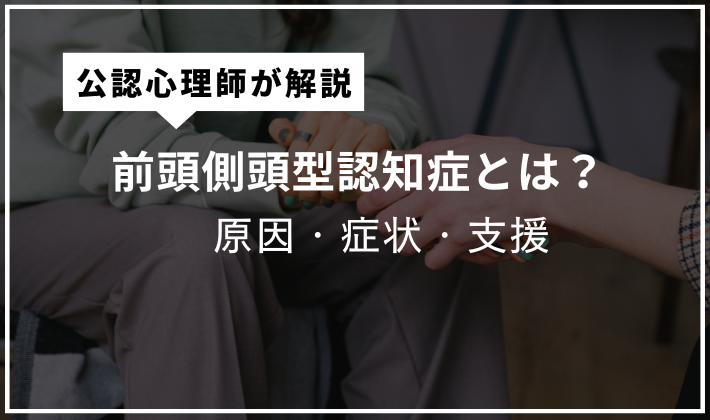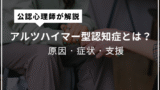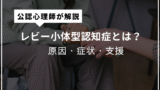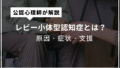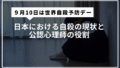皆さん、こんにちは!公認心理師のだびでです。
今回は認知症の中でも特に行動や性格の変化が目立つ「前頭側頭型認知症(FTD)」について解説します。
前頭側頭型認知症は全認知症の約5%を占め、比較的若い年齢で発症することが特徴です。一般的に50〜60代で発症することが多く、初期には記憶障害よりも行動や性格の変化が顕著に表れます。この病気を正しく理解することで、患者さんとその家族が少しでも暮らしやすくなります。
前頭側頭型認知症の原因
前頭側頭型認知症(FTD)は、脳の前頭葉と側頭葉が小さくなってしまう病気です。前頭葉は「他の人との関わり方」「感情のコントロール」「計画を立てる力」「判断する力」を担当し、側頭葉は「言葉を理解する」「記憶する」「感情を処理する」といった働きをしています。これらの部分が傷つくと、さまざまな症状が出てきます。
前頭側頭型認知症の原因はまだ完全にはわかっていませんが、タウタンパク質やTDP-43といった異常なタンパク質が脳に溜まることが関係していると考えられています。また、患者さんの約30~50%には家族に同じ病気の人がいて、遺伝が関係している可能性もあります。
前頭側頭型認知症の主な症状
前頭側頭型認知症は、損傷を受ける脳の部位によって主に3つのタイプに分けられます:
- 行動障害型(前頭側頭型認知症の代表的なタイプ)
- 意味性認知症(側頭葉前方部の萎縮が主)
- 進行性非流暢性失語症(左半球優位の萎縮)
それぞれのタイプについて詳しく見ていきましょう。
1. 行動障害型(行動異常型)
行動障害型は前頭側頭型認知症の中で最も一般的なタイプです。このタイプでは、人との関わり方や社会的な行動が大きく変化し、次のような特徴が見られます:
- 抑制が効かなくなる:周りを気にせず不適切な行動をとる、公共の場でも下品な発言をする。
- やる気がなくなる:周りのことに興味を示さず、家事や仕事への意欲がなくなる。
- 思いやりがなくなる:他の人の気持ちを理解できなくなり、冷たい態度をとる。
- 同じ行動を繰り返す:特定の動作を何度も繰り返したり、決まった時間に同じことをしたりする。
- 食事の習慣が変わる:食べ過ぎたり、偏った食事をしたり、何でも口に入れようとする。
この行動障害型は、初期段階では「性格が変わった」と思われることが多く、家族でさえも認知症だと気づかないことがあります。周りの人が「最近おかしい」「前はこんな人じゃなかった」と感じることは、診断の重要な手がかりとなります。
2. 意味性認知症
意味性認知症は、物の名前や意味が分からなくなっていく病気です。脳の側頭葉の前の部分が小さくなることで、次のような症状が出てきます:
- 言葉の意味が分からなくなる:「りんご」と言われても、それが何を指すのか理解できなくなります。
- 物の名前が言えなくなる:りんごを見ても「りんご」という言葉が出てこなくなります。
- 表面的な会話:一見普通に話せるように見えますが、実際は中身のない会話になっています。
- 顔が認識できなくなる:親しい人の顔でも誰なのか分からなくなることがあります。
意味性認知症の人は日常的な会話はスムーズにできることが多いので、周りの人は「ただの物忘れ」と思いがちです。しかし実際は「犬」や「車」といった基本的な言葉の意味さえ理解できなくなっていることがあります。
3. 進行性非流暢性失語
進行性非流暢性失語は、主に「話す」能力に問題が出るタイプです。脳の左側が縮むことで、次のような症状が出てきます:
- 言葉がスムーズに出ない:話し方がたどたどしくなり、言葉が出てくるまで時間がかかります
- 文法が使えなくなる:正しい文章を作ることができなくなります
- 発音が難しくなる:言葉を正しく発音することが困難になります
- 人の話は理解できる:自分では話しにくくても、他の人の言葉を理解する力は初期にはまだ残っています
進行性非流暢性失語症の人は、頭の中で考えていることをうまく言葉にできず苦しみますが、初期には物事を理解したり判断したりする力はまだ残っていることが多いです。そのため、周りの人とうまく会話ができなくなり、孤独や不安を感じやすくなります。
前頭側頭型認知症の治療
前頭側頭型認知症は現時点で完全に治す方法がありません。
治療の目標は症状の進行をゆっくりにしながら、その人がその人らしく生活できるよう支援することです。
薬物療法
残念ながら、今のところ前頭側頭型認知症を完全に治す薬はありません。薬物療法は主に症状を和らげるために使われます。
ただし、どの薬も副作用が現れる可能性があるので、医師との相談によって調整します。
環境調整
前頭側頭型認知症では、環境調整が重要です。
- 構造化された日課:規則正しい生活リズムを維持し、予測可能な環境を作る
- シンプルな環境:刺激が少なく、混乱を招きにくい環境を整える
- 視覚的サポート:言語理解が難しい場合は、絵や写真などの視覚的手がかりを活用する
- 社会的接触の管理:社会的に不適切な行動が見られる場合は、状況を予測して対応を考える
- 食行動への対応:過食や異食がある場合は、食べ物へのアクセスを管理する
また、音楽療法や芸術療法などの活動も、感情表現や心理的安定に役立つことがあります。
家族へのサポート
前頭側頭型認知症の介護は特に困難です。行動の問題や性格の変化、特に社会的に不適切な行動は、家族に大きな精神的負担をかけます。そのため、介護者へのサポートが非常に重要です:
- 教育と情報提供:症状の理解を深め、適切な対応方法を学ぶ
- レスパイトケア:介護者が休息をとれる時間を確保する
- 心理的サポート:介護者のストレスや悲嘆に対するカウンセリング
- 家族会:同じ状況にある家族との交流と情報共有
「なぜこんな行動をするのか」を理解することで、介護者の心理的負担が軽減されることがあります。行動の背景に脳の病気があることを理解し、本人を責めないことが大切です。
公認心理師の役割
前頭側頭型認知症においても、公認心理師は重要な役割を担います:
神経心理学検査
前頭側頭型認知症の評価では、特に前頭葉機能に焦点を当てた検査が重要です:
- 改訂長谷川式知能評価およびMMSE:代表的な認知機能を測定する検査。
- 前頭葉機能バッテリー(FAB):前頭葉の機能を評価する検査。
これらの検査結果は、診断の補助だけでなく、残存機能や強みを把握し、個別のケアプランを立てる上でも重要な情報となります。
本人・家族支援
前頭側頭型認知症では、特に家族支援が重要です:
- 心理教育:症状の背景にある脳の病気について説明し、理解を深める
- 行動マネジメント:問題行動への具体的な対応方法をアドバイスする
- 感情的サポート:家族の悲嘆やストレスに対するカウンセリング
まとめ
前頭側頭型認知症は、主に行動や性格の変化が特徴的な認知症です。記憶障害から始まるアルツハイマー型認知症や幻視が特徴的なレビー小体型認知症とは異なる症状を示します。
「何度も同じことを聞く」という典型的な認知症のイメージとは違い、「性格が変わった」「以前はこんな人ではなかった」という変化から始まることが多いため、初期には認知症と気づかれにくいのが特徴です。
前頭側頭型認知症の方への支援で最も重要なのは、「困った行動」の背景には脳の病気があることを理解することです。本人は自分の行動を制御することが難しくなっており、それは意図的なものではありません。適切な環境調整と家族支援により、本人も家族も少しでも穏やかに過ごせるようになることを目指しましょう。
認知症の方は「困った人」ではなく「困っている人」です。この視点を持つことで、支援の方向性が大きく変わります。前頭側頭型認知症の方とその家族が、尊厳を保ちながら生活できる社会を目指して、私たち専門家も努力を続けていきたいと思います。
参考文献
黒川由紀子・扇澤史子(編)(2018)『認知症の心理アセスメント はじめの一歩』医学書院
河野和彦. (2016). ぜんぶわかる認知症の事典: 4大認知症をわかりやすくビジュアル解説. 成美堂出版
川畑智 (2021). マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界. 文響社.